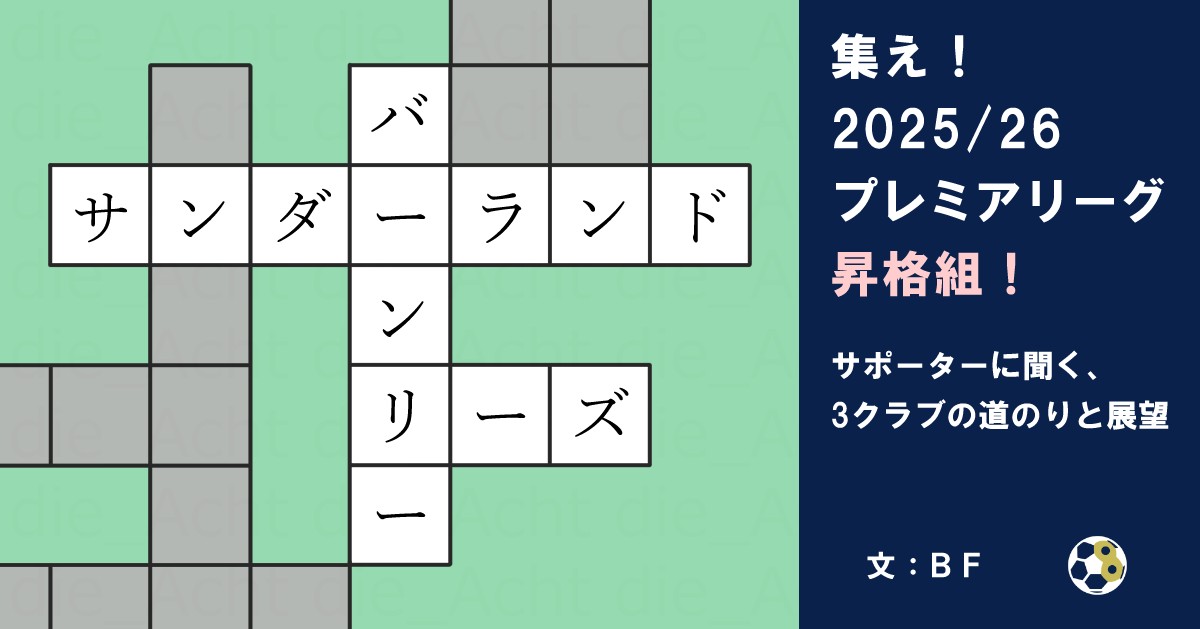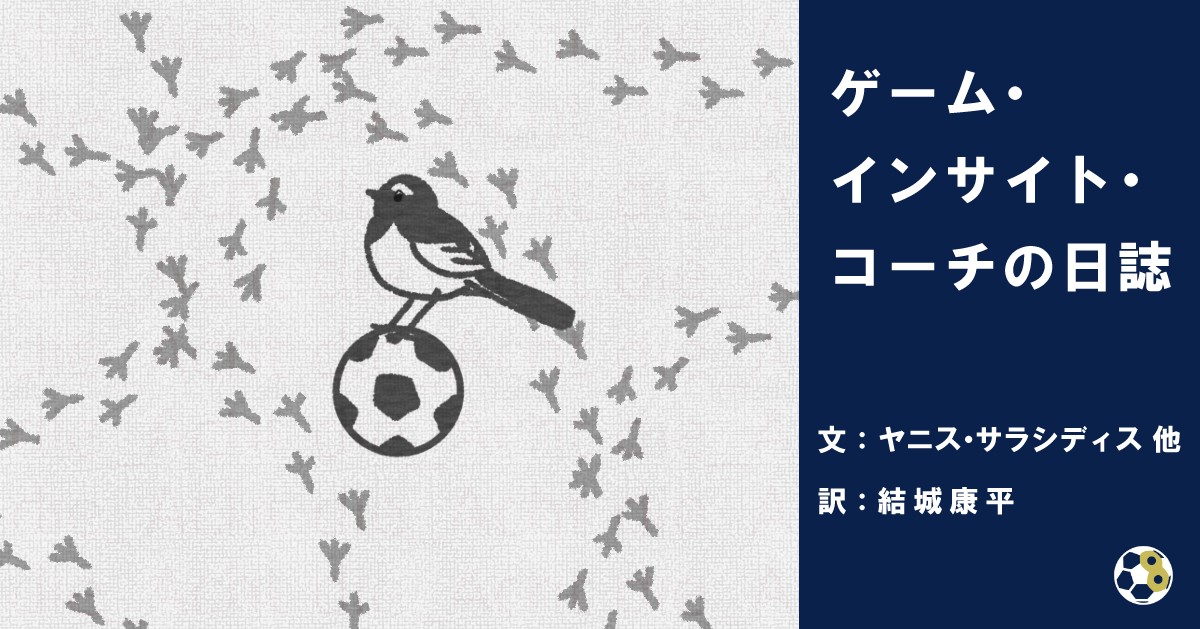チーム分析:トッテナム / アントニオ・コンテ

こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第76回は、コンテ監督の21/22シーズンのトッテナムにおける、ビルドアップの分析をお送りいたします。ぜひお楽しみください!
また、購読登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事や限定コンテンツを見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。
アントニオ・コンテは、ユベントスやイタリア代表で結果を残したイタリア人指揮官だ。守備的なフットボールを好むイメージが付き纏うイタリア人指導者だが、コンテは限られた戦力でも見事に攻撃を成立させる手腕を評価されている。
EURO2016では「前評判では最弱」とも呼ばれたチームを率いながら、複数のポジションでプレーする献身的なエマヌエレ・ジャッケリーニをスイッチにフォーメーションを頻繁に切り替え相手を幻惑。ベスト8にチームを導いた手腕は、誰もが認めるところだろう。
そんなコンテのサッカーの特徴は、「極限まで相手を引きつけるパスワークから、一気に前線のストライカーが速攻を仕掛ける」という点だ。例え相手がリバプールであっても、臆せずにGKからボールを繋いでいくことで、相手のプレッシングを引きつける。この一見ハイリスクなプレーの中には、配置や移動などのチーム戦術だけではなく、同数でもボールをキープできる一人ひとりの個人戦術が詰まっている。
今回は、トッテナムにおけるコンテのサッカーの分析を通して、ビルドアップにおけるチームとしての戦術と個人に求められる技術・戦術の両面を紐解いていく。

“Football is beautiful for this reason because it is unpredictable, if you don’t go with 100 per cent focus you risk losing.”
◇後方で奪われずに相手を引きつけるプレー
・1列目の越え方
いくら相手の背後を突く速攻が狙いといえども、いきなりGKやCBからロングボールを蹴ることはほとんどない。まずは相手のFWを越えることで、中盤の選手やSBを引き出し、前線の味方に良い形でボールを送ることを目指す。
本稿でははじめに、「相手のFWのラインをいかにして越えるか」を説明していく。
(1)ギャップを使う
基本的に、ハイプレスを仕掛けてくるチームは「最前線に2~3人のラインを形成」している。もしそのラインのギャップを使うことができれば、一気に相手FWのラインを越えて前進することが可能となる。

この時のギャップで受ける選手は流動的に変化する。この図のように、[3-4-2-1]の中央のCB(ダビンソン・サンチェスやエリック・ダイアー)がラインの背後に残る場合もあれば、3バックがスライドしてボランチ(ピエール・ホイビュアなど)が入ってくる場面もある。
また、このギャップに顔を出すポジショニングは、単にボールを受けるためだけではない。相手の間に立って意識させることで、プレスの足を止めることも狙いとなる。

FWが間を閉じなければギャップを通されてしまい、間を閉じるために中に絞ればCBまでの距離が遠くなりプレスをかけづらくなる。そうなれば、ギャップを使えなくてもCBを経由してのビルドアップが簡単になる。
特にハイプレスの強度が高い相手に対しては、「いかにして相手の足を止めるか」というのは非常に重要になる。プレスを引きつけたいとはいえ、飲み込まれるわけにはいかない。
また、相手のFWが3人の場合ギャップは2つ生まれるので、2人をギャップに立てる。

このように、相手のFWの枚数によってギャップに立つ人数は変わる。しかし、相手のFWラインを囲む4人の選手の立ち位置は変わらない。3バックの落とし方によって立つ人は変わるが、GK(ウーゴ・ロリス)の横とワイドの4箇所に人が入ってくるのが原則だろう。
(2)サイドへの浮き球
中央からの前進が難しい場合は、サイドのWBやCBへの浮き球で相手のFWのラインを越える。

特に、GKのロリスにとってサイドへの浮き球はプレスを受けた時の逃げ場となっており、意地でも無理に前線には蹴らず相手を引きつけようとする強い意志を感じる。
・サイドの三角形
ギャップを通せず、GKの隣に立つCB(ベン・デイヴィスやタンガンガ、ダイアー起用時はサンチェスが右センターバックに起用されることが多い)への展開からFWのラインを越えていく場合は、サイドでの三角形がポイントになる。まずは、三角形の作り方から見ていく。
GKの隣と両サイドには必ず人がいるので、その各サイドの2人に対してギャップに立つ中央の選手が3人目としてサポートに入る形が多い。間に合わない場合は他の中盤の選手が下がってくることもあるが、基本的に中央の選手がサイドの選手の真横に3人目として関わることで、三角形を形成する。

この三角形を作ることができたら、次は相手のプレスの方向を見ながらボールを展開し、前向きな選手を作る。まずは、分かりやすい3 vs 2の数的優位の状況から見ていく。
守備側は、数的不利の状況でボールにプレッシャーをかけようとする場合、パスコースを1本切りながらボールホルダーにアプローチしていく。そして、誘導した先で球際を作って奪おうとする。それに対し、攻撃側のトッテナムは「いかにして球際を作らせないか」がポイントとなる。
そこで、「相手が切ろうとしているパスコースを外して、新たにパスコースを作り出す動き」がとても重要になる。相手FWが中からCBにプレスをかけてくる場合は、中央のギャップに立っていた選手が左右に動き直し、外からのアプローチの場合はサイドの選手が高さを変えてサポートする。

守備側(相手)としては、そもそもの誘導がうまくいかなければ球際は作れない。また、「ボールにプレスをかけている選手がパスコースを消せている」という前提で他の選手は守る選手を決めるので、そこを剥がされると一発でフリーマンを作られる。シンプルだが、一番効果的なプレスの剥がし方だ。
では、ボールホルダーへの寄せが早く動き直してパスコースを作り直せず、相手が誘導する先にパスを出さなければならない場合は、どのようにプレスを剥がすのだろうか。
その場合の工夫として、まずはワンタッチのパスで3人目の選手へ届けることや、後ろに戻りながら受けることで背中からのプレッシャーが届かないようにする動きが挙げられる。特に、コンテのトッテナムでは中央の選手が素早く3人目として入ってくる動きが徹底されているため、常に2本のパスコースを確保できるのでワンタッチでボールを動かすことができ、プレッシャーの回避が可能となっている。

そして、後ろに戻りながら受けるプレーは、相手が同数でプレッシャーをかけて来たときにより重要性を持つ。同数ではめられた場合は、「GKの隣に立つCBへの展開からFWのラインを越えていく」という本筋の狙いにもあるように、ライン間にいる前線の選手に一気にボールを届けて速攻を仕掛けたい。
しかし、まずは良い形でボールを届けられる状況を作り出さなければならない。そのために、同数の中でも前向きな選手を作ることが大切になる。したがって、同数の状況でもボールを繋ぐ必要があり、「後ろに戻りながらスペースを作ってボールを受けるサポート」が重要となる。

図に示すように、降りてきてスペースで受けることで球際を作らせず、相手から遠い足でワンタッチでライン間へ送るプレーだ。もし数的優位を作れているのであれば、ワンタッチで横の選手に渡して前向きの選手を作れるが、3人目が相手にマークされている場合は相手から遠い逆足でライン間へボールを送る。(上図:左サイドでの崩し)
また、2人目の選手が相手にタイトにマークされて逆足ダイレクトでライン間にボールを出せない場合は、背負った状態でボールを受け、後ろの選手がもう一度受け直して前向きの状態で縦パスを送る(上図:右サイドでの崩し)。
もちろん、このように前向きな選手を作れない場合もある。その場合は、4人目の選手を介して逆サイドへの展開を目指しプレスを回避する。

逆サイドの中盤の選手やGKが逃げ道となることによって、プレッシャーを受けているボールサイドから展開していく。一気に逆サイドへのロングボールを飛ばすオプションもあり、うまくプレスを回避できれば逆サイドから前進していくことができる。
このように、同数でプレッシャーを受けている場面でボールを繋ぐのはリスクではあるが、状況を打開することで前線の優位を活かすことがコンテの狙いなので、トッテナムの選手たちは慌てずに繋いでいく。
続いては、「前線でどのようにボールを受けて速攻を仕掛けるのか」を解説してみよう。
◇ボールを引き出す前線の動き
後方でボールを繋いで相手を引きつけたら、次はライン間のスペースで前線の選手が連動した動きからボールを引き出し、速攻へ繋げる。その時も、「いかにして前向きな選手を作ることができるか」が鍵になっている。
基本的に、ライン間でボールを引き出すことが多いのがシャドーの選手(ソン・フンミンやルーカス、クルゼフスキが起用されることが多い)だ。サイドの三角形が同数でプレッシャーを受けている時に、彼らがダイヤモンドの頂点としてボールを引き出す。
もちろん、ここで前を向ければベストだが、相手のプレッシャーを受けている場合は背負って落とす流れで前向きの選手を作る。これは、サイドの三角形で同数を打開する時と同じ原則である。

加えて、ライン間で前を向いたタイミングで逆サイドのシャドーとWBが背後への動き出しを見せ、手薄の逆サイドへ展開することで攻撃を加速させる形も多く見られる。

この逆サイドへ飛ばす流れは、最初のボール出しでギャップを使えたり、サイドの三角形で数的優位から中央で前を向けた時にも見られる。中央のスペースで前を向いた後は大外のWBへ展開、というプレーで手薄なサイドを素早く使う速攻につなげることができ、トッテナムでよく見られる形だ。
また、シャドーへボールを入れるタイミングでマークが激しい場合は、最前線のCF(主にハリー・ケイン)が降りてきてボールを引き出す。この場合、シャドーが背後を取る動きを見せながらCFが降りてボールを引き出すので、守備側(相手)のCBが前に出てプレスをかけにいくのは難しい。仮に出ていったとしても、背後のスペースを突かれるリスクを負うことになる。

このように、前線3枚による前後の揺さぶりでボールを引き出し、手薄になっているDFラインを越えていこうとする形がコンテの最大の狙いだろう。ここまで、前線の動きと後方の三角形と分けて見てきたが、ベースとなっているのは「降りてきて受ける」「ボールホルダーを追い越す」というポストプレーの連続だと言える。
この「降りてきて受ける」という動きで相手守備者を引き出し、「追い越す」動きで背後を突いていく形が、現在トッテナムで体現されているコンテのサッカーにおける基本である。

Welcome, @richarlison97! 🔥
#WelcomeRicharlison
また、エバートンから獲得を発表したブラジル代表のリシャルリソンはフィジカルバトルを厭わない武闘派FWで、機動力も兼ね備えている。ボールを動かしながら連動してゴールに迫るトッテナムにとって、面白い補強になるのではないだろうか。
◇まとめ
後方で引きつけて相手を誘い出し、一気に背後のスペースをアタックしていくコンテのトッテナムやインテルのサッカーからは、「どのように相手のプレスを見ながらビルドアップし、同数でも冷静にボールを繋いでいくか」という要素を学ぶことができる。
「どのように選手を動かし数的優位を作り出してボールを動かすか」、「同数を作ってボールを奪いに行くか」、というチーム戦術。
そこからさらに深堀りして、「相手の矢印を見てプレーをする」、「動き直してパスコースを確保する」、「マーカーを振り切って一瞬フリーになる」といった個人戦術が詰まっているので、ぜひ注目して観てほしい。
文:白水優樹(@shiroe___s)
ディ アハト第76回「チーム分析:トッテナム / アントニオ・コンテ」、お楽しみいただけましたか?
記事の感想については、TwitterなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!
ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら