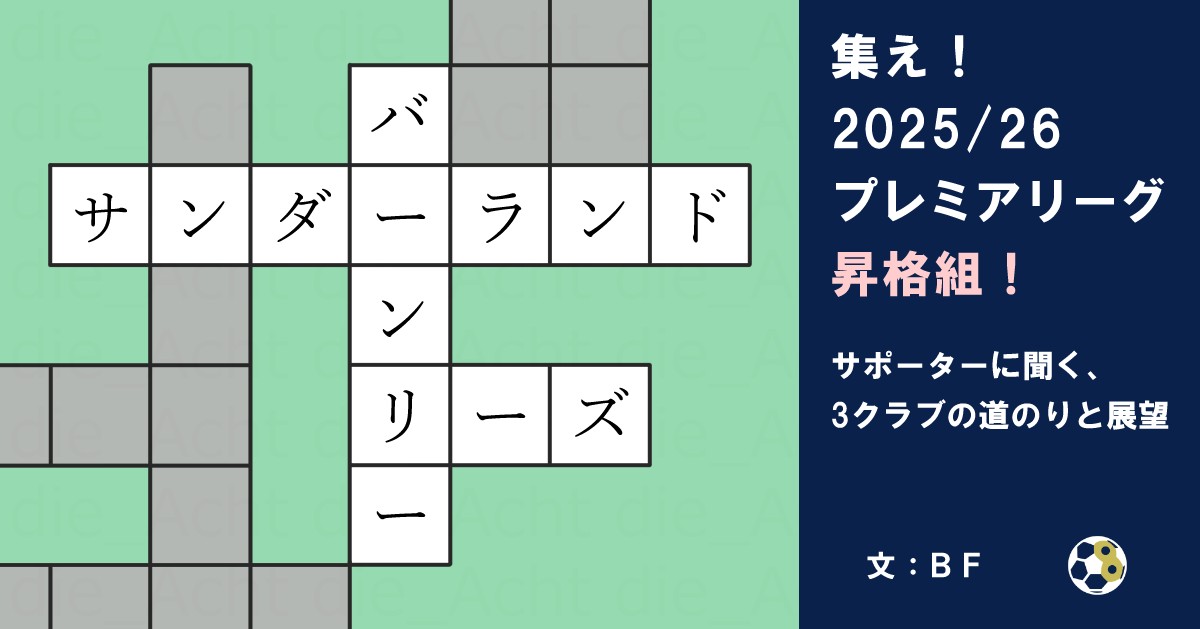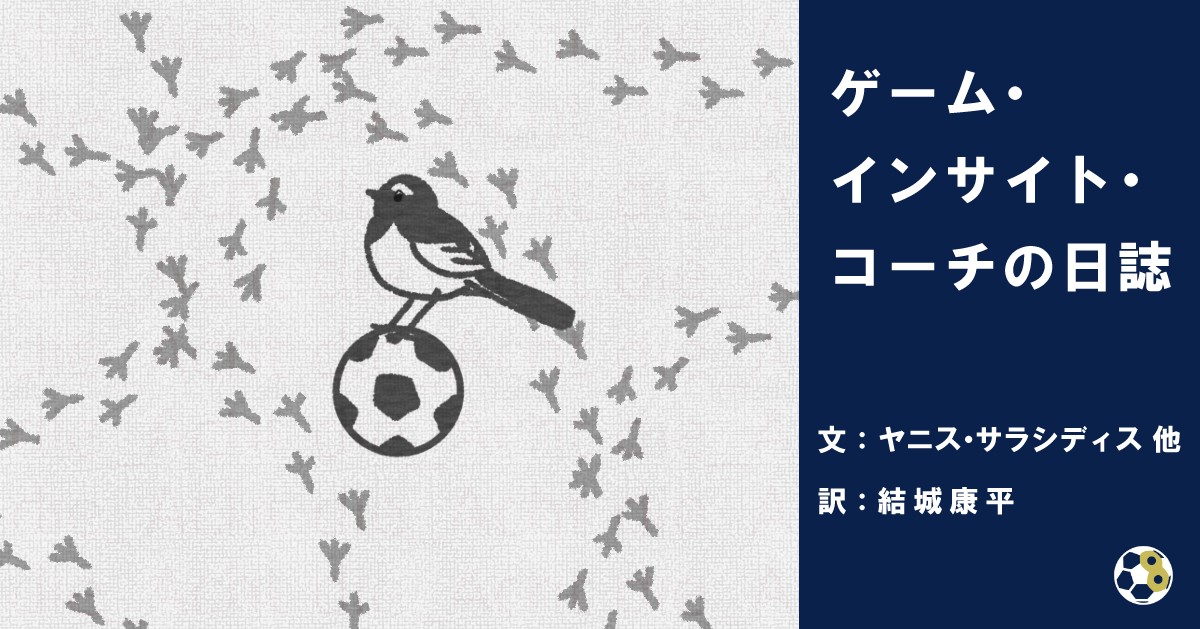マッチレビュー 天皇杯決勝戦 浦和レッズvs大分トリニータ

こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第37回は2021年12月19日に国立競技場にて行われた、第101回天皇杯決勝戦のマッチレビューをお届けします。ぜひお楽しみください!
また、購読登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事や限定コンテンツを見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。
サッカーは、人々の心を揺さぶるものだ。大分トリニータの快進撃は、私にウィガン・アスレティックFCと過ごした日々を思い出させた。
あれは2012 / 13シーズンのこと。プレミアリーグ降格争いの最中、すべてのリーグ戦に集中しなければならない状況でウィガンはカップ戦を勝ち進んでいた。目の前にはクラブ設立史上、初のタイトル。
FAカップを勝ち進みながら、リーグの終盤戦に挑むという最高難易度のミッションに、智将ロベルト・マルティネスは策略を尽くした。決勝戦の相手はマンチェスター・シティ。魔法のステッキを持った天才ダビド・シルバは、ただボールを触るだけで砂を金に変えるようなプレーでチャンスを生んでいく。今もその実力を発揮する男を中心とした攻撃陣は、驚異的な破壊力でウィガンを脅かしていた。
しかし、守りに徹したウィガンは数少ない勝機に全力を注ぐ。控えとしてシーズンの大半を過ごしたMFベン・ワトソンがコーナーキックから値千金のゴールを決めた瞬間は、ウィガンサポーターが忘れられない「伏兵の一撃」だった。奇跡の色は何色だろう?と問われたら、私はあの夜に見たスタンドを染めた「青」だと答える。
色味は違うものの、大分トリニータも「青」をチームカラーにしている。そして、戦力差を補うことに長けた戦術家に率いられているところも、少しウィガンと似ていた。
また、ポゼッションをベースにしたチームでリーグに旋風を巻き起こしながら、決勝に進出した今シーズンは苦しんでいたことも共通しており、陳腐な言葉で言えば運命を感じさせた。当然その先の運命はそれぞれのクラブが切り開いていくものであり、3部相当のリーグでプレミアリーグ復帰を目指しているウィガンと、今後の大分トリニータは違った道を歩むだろう。それでも、瞬間的に「クラブ史に残る決勝に挑む」クラブの運命は私の中で重なった。

しかし、個人的な趣味嗜好を除いて考えれば、十分に浦和レッズも勝利への飢えを抱えていた。新指揮官リカルド・ロドリゲスは初タイトルとACLへの挑戦権獲得に燃え、準決勝では宇賀神友弥が完璧な先制ゴールを沈める。
シーズンいっぱいでチームを去る阿部勇樹、槙野智章、宇賀神友弥のためにも、天皇杯は喉から手が出るほど欲しいタイトルだったに違いない。戴冠を目指し、彼らも厄介なダークホースへと挑んだ。

軍師と共に深淵から這い上がってきた”群青”か。
101回目の天皇杯決勝は、12/19(日)14:00〜キックオフ!
▶️lnky.jp/wwEk8lX
ゲーム開始から、ペースを握ったのは浦和。4-3-1-2の大分は中央からハイプレスでビルドアップを阻害する意図があり、トップ下のポジションで中盤の起点を潰すことを狙いとしていた。本来は一列後ろを本職にする下田北斗を前に置くシステムは、センターバックと中盤1枚で構成される「最後列3枚のビルドアップ」を牽制する大分の策だった。下図のように、2トップとトップ下が連携すれば「3枚」に同数でプレッシングを仕掛けやすい。
しかし、指揮官ロドリゲスは中盤にボランチを2枚並べた2-2のビルドアップを選択。下田が片方をマークしても中央にフリーマンが存在するシステムは、堅固にブロックを構築したい大分の3センターに対して効果的だった。伊藤敦樹と柴戸海は慎重にボールを引き出しながらゲームを構築し、大分のショートカウンターを封じていた。

パターンとして観察されたのは、中央のフリーマンがサイドバックと連携しながら3センターの両脇を前に動かし、大外に展開しながら3センターがいたはずのハーフスペースに侵入するという浦和の崩しだった。アンカーに起用された小林裕紀の左右に江坂任やサイドハーフが侵入し、大分の守備陣を嫌がらせる。
特に左サイドからの攻撃は強力で、酒井宏樹が起点として機能。下がってきた関根貴大が低めから加速してドリブルを仕掛け、ハーフスペースにはトップ下の江坂だけでなく左サイドの小泉佳穂が逆サイドまで流れながら数的優位を担保していく。
この試合、どちらかというと攻撃の構築よりもバランス感覚で磐石さを感じさせた浦和だったが、1.5列目の動かし方は位置的、数的な優位を意識しながらデザインされており、その結果として先制ゴールが生まれている。大分からすればボールを取り返した小泉のプレーでファールを取って貰いたいところだったが、笛は鳴らずにプレー続行。序盤から鋭い突破を繰り返していた関根がサイド深くまで侵入すると、絶妙な折り返しが中で待つ江坂へと繋がる。大分守備陣の間隙を縫うように放たれたシュートはゴールネットを揺らし、柏レイソルから加入した江坂が大一番でその価値を示した。
大分の守備陣は小泉のポジションチェンジで過度に片方のサイドに寄せられたことでバランスを崩しており、密集したエリアだからこそ小泉の即時奪回と関根のドリブル突破が可能となった。
密集地で個の強さと賢さを活かし、浦和が地力を見せつける。奇跡を諦めない大分だったが、前半は浦和のゾーンディフェンスになかなか突破口が見つからない。江坂がトップ下のようにプレーする4-4-1-1は、大きく崩れない距離感で守れていた。
唯一、大分が突破口として狙うべきだった浦和の隙は、サイドバックにボールが入ったタイミングで浦和の両サイドハーフが寄せてくる瞬間で、彼らがワンテンポ先に動くことでゾーンが崩れている場面も少なくなかった。

実際、センターバックからサイドバックへのパスをダイレクトでリターンしたり、サイドバックへのパスを囮にして相手を誘えれば、サイドバックのゾーンへ縦パスを当てられる場面も目立った。しかし、大分が苦しかったのは外に流れたFWやセントラルハーフが浦和のサイドバック陣に競り負けることが多かったことだ。せっかく縦にボールを届けてもサイドでの突破は難しく、逆に左サイドは酒井と関根が重いカウンターパンチを繰り出してくる。こうなってしまうと積極的な策は難しく、大分は防戦の時間が長くなってしまった。
しかし、今シーズンで大分での指導を終える片野坂監督は、後半に一手でチームを変貌させる。
トップ下で起用された下田を本職であるボランチに戻すと、4-2-2-2のようなフォーメーションに変更。オフ・ザ・ボールの技術に優れた町田也真人とFWが本職の渡邉新太をゴールに近づけたことで、チームの攻撃力は倍増する。守備面でも小泉と関根がハーフスペースに侵入しづらくなり、攻守両面でチームの状況は好転していく。守備ではエンリケ・トレヴィザンとペレイラが浦和のカウンターを個の力でシャットアウトし、ハイラインで仕掛けるチームを支えていたことも見逃せない。

下田のスルーパスでチャンスを作った場面は典型的で、MFがハーフスペースに立つことで相手守備陣の注意を集中させている。その背後でFWが抜けていく動きが、惜しいチャンスに繋がった。渡邉も積極的にドリブルを仕掛ける場面を増やし、攻撃を活性化させていった。
そして、値千金の同点ゴールが生まれる。アディショナルタイム、1秒でも急いでボールを蹴りたいところで大分は冷静にショートパスを選択。チームプレーに徹していた下田が逆足で浮かせたボールに、最後はペレイラが押し込む。
しかし、幕切れは更に衝撃的だった。途中から投入された今季でチームを去る槙野が「お祭り男」の名に恥じないスーパーゴールを決めたのだ。ミドルシュートのコースを変えたヘディングがゴールに吸い込まれ、一度「奇跡を信じた」大分サポーターの夢は一瞬で散ってしまった。
好調を保っていた大分の守護神、高木駿がハイボールを自ら処理する場面が増えていたことは小さな「悪い前兆」であり、最後の場面でもシュートへの準備が一瞬だけ間に合わなかった。
浦和を追い詰めて大分のサポーターに希望を与えた智将は、来シーズンからガンバ大阪で新しい挑戦をスタートする。大分にとってシーズンの集大成となった天皇杯の決勝戦は、多くの選手にとって忘れられない思い出になったはずだ。
浦和も先制ゴールからの冷静なゲーム運びで、チームとしての成熟を感じさせた。普段は正月の風物詩である天皇杯決勝が年末に開催されたのは新鮮だったが、2チームが全力を尽くしたことで歴史的な「終盤のゴール」が連続するゲームになった。
シーズンの終わりを告げるのに相応しい激戦は、駆け抜けた2021シーズンに加わる新たな物語として、我々の思い出に深く刻まれるだろう。
文:結城康平(@yuukikouhei)
ディ アハト第37回「マッチレビュー 天皇杯決勝 浦和レッズvs大分トリニータ」、お楽しみいただけましたか?
記事の感想については、TwitterなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!
ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら