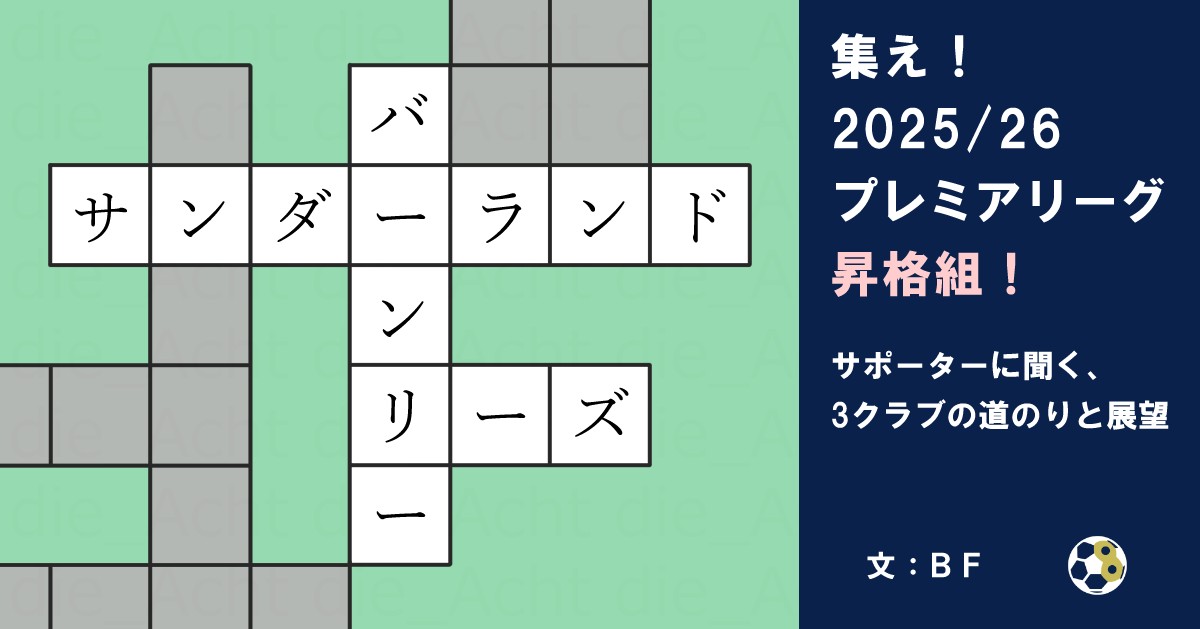ゲーム・インサイト・コーチの日誌
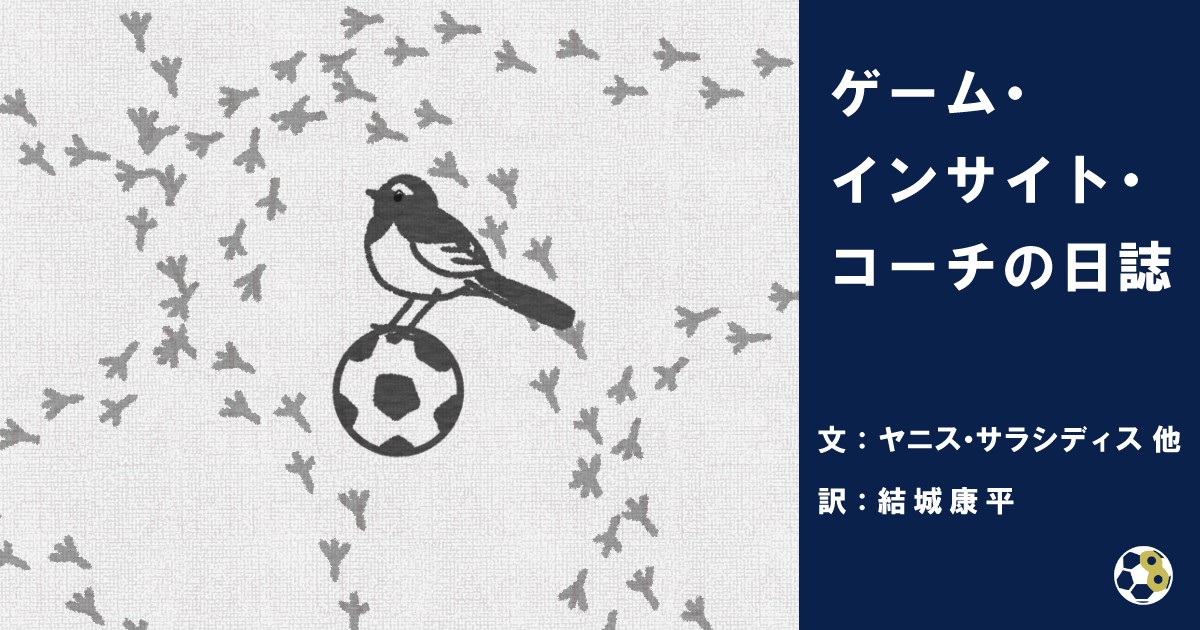
こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第106回では、日々現場で選手と向き合う若きフットボール指導者たちによる記事をお届けします。彼らがどのような問いを立て、何を考え、どういった要素に注目し、そしてコミュニケーションやトレーニングに落とし込んでいるのか、その思考をのぞいてみましょう。ぜひお楽しみください!
またニュースレターに読者登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事を見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。
以下に記すものは 、プレーの設計図ではない。これは、ゲーム・インサイトの最前線で働くコーチたちによる、生々しく飾り気のない対話──テキスト、ビデオ通話、そして瞬発する「気づき」ーを編集せずに記録した「現場にしかない知見」である。
読みやすくするためにいくつかの見出しを付与したが、以下に続くのはすべて、ひとつの問いを巡る断片的な連なりである。
「チーム内で最も創造的で、適応的で、自律的な選手をどのように育成するか?」
「私の最大の資質は、どのような批判であれ受け入れ、耳を傾け、より大きな公益のために変わる意思があることである」
◇ゲーム・インサイト・コーチングとは、何か?
複数の参照点(位置・瞬間・タイミング・スピード・チームメイト・相手選手など様々な要素)とそれらがフットボールにおける行動におよぼす影響を理解することは、極めて重要である。ある人物が、参照点が各アクションの有効性に与えるごく僅かな影響に対する精緻に調整された感受性を持ち合わせていない場合、その人物を真にワールドクラスのインサイト・コーチと考えることはできない。
さらに、その人物は多様なコーチングメソッドに関する深遠な知識を有すると同時に、情緒的な選手とのつながりを築くスキルを兼ね備えていなければならない。すなわち、参照点とそれらの相互関係を精緻に把握し、それを選手の行動における有効性を通じて解釈できる能力が求められるのである。
世界水準のゲーム・インサイト・コーチに求められる主要な3つの資質は、以下の通りである。
-
個々の選手に対して、個人のゲーム・インサイトを育成するための参照的コーチングに従事する者。重要なのは、問題が発生したフットボール行為における 「CDE」段階(コミュニケーション・意思決定の段階) を通して、主要な問題を定義する方法を把握していることである。さらに、選手を重要な結論へと導く問いかけ(アクティブラーニング)によって、これらすべてを体系的に構築する方法を知っていなければならない。
-
フィールド内外での学習を指導するために、スキル適応を深く理解していること(情報をどのように共有し、どの間隔で共有するか──意図的フィードバック・ループの活用を含む)。教育学/教授法における熟達が求められる。
-
状況的コーチングを理解し、選手から望ましい行動を引き出すように演習(エクササイズ)を設計する術を知っていること。演習は、それ自体が「意味を伝えるもの」でなければならない。熟練したコーチングとは、設計によってコーチが選手に経験させたい行動を、言葉を発することなく喚起させる状態を指す。
方法論におけるカギとなる問いは、「各瞬間における最適なポジショニングをいかに定義するか」である。選手自身が、どのポジションをいつ使うのが最適かを認知していなければならない。
これは初期学習段階においてはコーチの役割になり得るが、後には選手自身が試合中に相手の動きやチームメイトの動きを認識し、自らの資質およびチームメイトの資質に基づいてポジショニングと実行しようとするアクションを最適化しなければならない。もし方法論がこのようなポジショニングにおける柔軟性を規定していない場合、多数の状況において非最適的となるだろう。
◇選手の自己という参照点
フットボールは、関係性における出発点である。もしコーチが選手のフットボールにおけるプレーの効率を向上させるためにあらゆる努力を払っていると選手が感じれば、ほとんどの選手は自然に心を開き、より親密な問題にも取り組むようになる。
行動に関する「何を(What)」と「どのように(How)」が明確でなければ、信頼を構築するための誠実な基盤は存在しない。行動の「何」と「どのように」が明確に定義されていなければ、指導者は選手に対して率直になれないし、深い関係性を築くこともできない。これは関係性が構築・深化される出発点であり、選手を理解するために時間を費やしてきたことを示す証左でもある。
選手を詳細に診断するために、私は各選手について10~15試合を観察する──その選手にのみすべての注意を向けて。すべての行動とトリガーをアクション・ランゲージで書き留める。これがあらゆるプロセスの出発点である。そうすることで、特定のゾーンにおいてどの行動をその選手が最も頻繁に行い、どの程度のアクションが有効なのかが明らかになる。
したがって主要な命題は次の通り──個々の選手を詳細に把握していなければ、チームレベルでゲームを最大限に最適化するための前提条件を持たない、ということである。ゆえに我々は、選手を個別水準で分析し、最適化することにおいてエキスパートになる必要があるのだ。
私の経験では、選手は1試合において平均して約50回、チームの意図に大きく寄与し得る行為を行っている。プレーレベルが高くなるほど、その数はやや増加する傾向にある。我々の役割は、選手が最高の意図(チームの意図への貢献として)を認識し遂行するのを助けることであり、より重要なのはそれを選手自身の行動と整合させて行わせることである。
ここで重要な出発点に立ち返る。選手は自らのいくつかの主要な長所といくつかの主要な弱点を深く理解していなければならない。選手が潜在能力を発揮することを望むのであれば、この自己認識は不可欠である(これは、続く「チームメイトという参照点」で論じるシナジーのための重要な前提条件でもある)。要点は、出発点は恣意的なプレーモデルではなく選手自身であるということだ。すべてのシステムの初動はチーム内の選手であり、出発点をそのように理解しないのであれば、フットボールを理解しているとはいえない。
我々は、各選手が試合をどのように知覚しているかを親密に把握しなければならない。そして、彼らのもっとも有効な行動およびチームメイトのもっとも有効な行動に即して、選手自身の試合に対する知覚をいかに改善するかを知る必要がある──これが我々の定義する「戦術」となる。
私は文字通り、各選手にそれぞれ異なる世界を見出す。成功のカギは間違いなく、もっとも高いシナジー効果を生む選手同士を組み合わせることにある。これを可能にするためには、我々の分析を従来とは異なる次元で機能させなければならない。
ある選手がポジション・方向・タイミング・スピードごとに効果的に実行し得るあらゆるアクションを詳細に記述できれば、その選手のゲームについてほとんどすべてを把握したことになる。そうして初めて、その行動に最も適合するゾーン内の選手を特定することができる。たとえば私はすべてのアクションを追跡するが、分析の最終段階では特に成功率が高いアクションと失敗率が高いアクションのみを考慮する。これら2つのカテゴリーが、選手を深く理解する際に我々が探し求める主要な分類である。
これによって、選手の強みをどのように強調するか、次いで弱点は何か、そしてどのプレーの側面を隠す必要があるかを明確にできる。
近年の「自律的な選手ポジショニング」の議題に関していえば、サイドバックのポジショニングを準備する際には、我々は参照的コーチングを用いて、異なるプレッシング・システムを想定した状況を提示する。選手には状況を読み取り、どこに・なぜその位置を取る必要があるのかを一貫して理解させることを要求する。
基礎的なトレーニングの段階で各選手は、自らの資質に常に整合した個別の意図を考慮しつつ、ポジショニングに関する自律的理解を育まなければならない。このトレーニングは継続的であり、絶えず洗練される。複数のプレッシング・システムを用いる相手に対しては、我々は各試合ごとに選手を特別に準備し、各システムに対して個々の意図をいかに遂行するかを指導する。こうした特定試合の準備は週間トレーニング過程の70%を占めるべきであり、残りの30%は年間の選手育成計画に沿った一般的な選手育成に充てられるべきである。
各選手が自らのスキルセットに応じ、チームの意図に貢献することは極めて重要である。選手の特別なスキルと主要な弱点を理解することは不可欠である。選手は、自らの長所を発揮し、弱点を隠すことを指導されることで最適化されるべきであり、これを多様な文脈で実行できなければならない。こうした選手は回復力があり、適応的であり、自分が何者であるかや誰であるかを理解すると同時に、チームメイトや対戦相手についても同様の理解を有している。
もし選手の特別な技能がワンタッチのロングレンジ・パスであるならば、それを可能な限り頻繁に、かつ多様な文脈で活用できるよう習得させる必要がある。数種類の特別なスキルを有し、それらを用いて試合の中で自己を効果的に表現できる選手は、ワールドクラスに到達し得る。
選手は、自らの強みおよびチームメイトの強みの視点からフットボールを学ぶ必要がある。意思決定において相手の特性をより大きく考慮に入れることは、選手がチーム内のコミュニケーションを完全に理解した段階において段階的に導入されるべきだ。もしその段階より早く相手を考慮すると、認知過程に過度の負荷となり、悪影響を生じさせる可能性がある。したがって、優先順位は自己・チームメイト・相手の順で明確にしておくことが不可欠である。
選手が自己の主要な資質とそれがパフォーマンスにおよぼす影響を把握している場合に初めて、これらの行為の効率性を向上させる支援が可能になる。ここで、4-4-2の守備を想定し、次の2つの状況を考える。1つは前線がプレス可能な射程内にいる場合、もう1つは前線がその射程内にはいないが、選手個々の資質から考えれば本来プレス可能であったはずの場面である。
ここで問うべきは、コーチがどのような障壁によって、効果的なプレス射程を取らせる方法/より良いポジショニング、プレスのトリガーを認識させる方法、およびプレス射程外にいる際に(積極的に飛び出せない状況でも)相手の進攻につながる選択肢を阻止する方法を教えられないのか、という点である。どの選手がプレスを開始できたのか、その理由は何か。また、効果的なプレスの前提条件を整えるために、他の選手はどのような意図を果たす必要があったのか。
各選手については、実際には遂行されなかったが遂行可能な意図/しかし必要な行動を実行する資質は持っている場合)を定義する必要がある。これは選手の現在の状態と潜在能力との乖離を示すものである。次に、試合においてもっとも頻繁に反復される意図、すなわちパフォーマンスに最も大きく影響する意図を特定する。これらが個人の育成における優先事項となる。
分析のもう一側面は、次戦で発生する可能性が高い相互作用(チームメイトとのシナジーを対戦相手の分析と重ね合わせたもの)を評価することである。これら2つのカテゴリーの間に重複が見出された場合、それらが実際の試合中に取り組むべき行動である。
具体的な問いとしては、試合中にその選手が「プレスをかける選手/相手の前進を阻止する選手」になり得た場面が何回あったのに、タイミングを認識できずに相手が進行する選択肢をどうして潰すことができなかったのか、という点である。なぜその認識が欠如したのか。選手が特定の行動を遂行できなかった理由となる根源的な「何」と「なぜ」を把握すれば、何を・どのように・誰と取り組むべきかという明確な方針が得られる。
選手は、1つの原則だ。しかしそれが成立するのは、位置・瞬間・タイミング・スピードに関する一般的な原理が存在する時に限られる。そうでなければ、意思決定を根拠づける客観的参照点が存在せず、したがって個別な最適化は不可能である。
もしポジションに関する原理が「必要な範囲において、可能な限り相手ゴールに近づくこと」であるなら、選手はフットボールの動的参照および静的参照に照らして、特定の行動における自身にとっての理想的なポジションを明確に自己調整することができる。これは自分自身・チームメイト・相手の資質を考慮した上で行われる。
選手が自覚していない事柄は、我々が参照的コーチングを通じて継続的に指摘し、それが徐々に選手のフットボール観の一部となる。初めは意識的であるが、最終的には無意識的に遂行できるようになる──知識の最高段階は「無意識に有能」である。
選手の主要な資質と弱点を識別し、それらを最適化する最良の方法を見出す能力は、平均的なゲームインサイトコーチと卓越したコーチを区別する要因である。選手を観察する際は常に次の問いを自らに投げかけるべきである。すなわち「彼のプレーはどの資質に基づくべきか、どの弱点を隠す必要があるか、そして彼のサッカー行動における『How(どのようにプレーを遂行するか)』を最適化するために、参照的および状況的コーチングの最も効果的な手法は何か」。
◇チームメイトという参照点
私とあなたが互いの強み、すなわち互いの“Xファクター”を深く理解しているなら、我々は単なる予測を越えて、まるでテレパシーのような相互理解に到達する。これは明確な優位性である。
私はこう考える。ボールにプレッシャーがかかっている場合、ボールを持たない選手がゲームの主導権を握り、一方でボールがプレッシャー下にない場合は、ボールを持つ選手が味方の動きを主導する。基本的には「より重要な存在」の機能は常に変化しており、それを固定的に捉えるべきではない。ボールは試合中に、何度もオープンになったりクローズドになったりしている(=ボールの進行における相対的時間と空間)。
ゲームは究極的に、2人以上の選手間にシナジーが生じる状況によって規定される。たとえば私が私にしか出せない独特のパスを出せる状況となり、あなたがその受け手としてあなた固有のターンをしながらボールを受けるという資質を発揮するなら、効果的な相互作用が成立する。選手にはこうした視点を通してゲームを観ることを教える必要がある。試合は我々の資質から生まれるシナジー効果を活用する機会によって支配される。
「チームメイト」という参照枠における目的は、まず選手自身が自らの資質に対する認知を高め、次にチームメイトの資質を理解させることで、行動の協調を改善することである。想定例を挙げよう。チームメイトXはプレッシャー下で優れており、背後からプレッシャーを受けている場合でもボールを展開しながら短~中距離のパスを通す能力を持っている。したがって攻撃の開始局面では、相手のプレス反応を誘発するような形で彼にボールを預けるべきであり、そうすることでスペースをより効果的に活用できる。
各選手が自らの主要ないくつかの強みとチームメイトの主要ないくつかの強みを把握し、それに基づいて意思決定を行うならば、最大限のシナジーが生まれるための前提条件を形成することができるはずだ。
ここで想像してみてほしい。あなたと私はセンターバックであり、守備上の相互作用に課題を抱えている。とりわけ、相手のアタッカーに対して2対2の状況を処理しなければならない場面での問題だ。こうした状況を、それぞれの資質を踏まえてどのように解決するかを知っておく必要がある。もし自分たちだけで解決できないのであれば、最寄りの選手からのサポートをどのように得るかを把握しておかなければならない。
別の例として、私が最終ラインの背後を守ることに課題を抱えるセンターバックであるとしよう。その場合、私にとって何が最も重要になるだろうか。答えは行動を読み取り、縦の間合いを段階的に詰めることを学ぶこと、そして最終ライン前のスペースを埋めるようにチームメイトに指示することだ。すべては自己理解とチームメイトの理解に依存している。
この種の暗黙の理解はトレーニングを通じて獲得されるが、選手同士でこの知識を能動的に移転することによってさらに増幅され、互いの理解の質と深さが深化する。これが、明確な参照を持つことの強みになる。
広義では、これを「洗練されたフットボール学派」と呼ぶべきだろう。洗練されたフットボールとは、各個の選手が自己・チームメイト・相手を主要な参照点として、空間と時間を自律的に解釈することによって定義される。より短い時間・限られた空間の中で、より効率的かつ効果的にコミュニケーション・意思決定・プレーの遂行を行う能力は、最終的かつ決定的な参照である相手によって自ずと制約されている。
◇対戦相手という参照点
私にとってのカギは、次の命題を徹底的に考えることである──限りなく少ない情報で、各選手の効率を可能な限り高めるために、対戦相手について各選手に何を伝えなければならないのか。
「相手」という参照点について論じる際には、これをより詳述するべきタイミングだ。相手の参照は、我々のシナジーを追加的に最適化する装置として機能する。想像してほしい。あなたと私には有意な差を生むことのできる5つの相互作用、すなわち我々の主要なシナジーがあるとする。しかし相手はそのうち3つに対して巧みに反応して無効化してしまい、残りの2つに対してのみ十分に対処できない場合がある。
たとえば、右ハーフスペースから裏へのワンツーを行うことが非常に有効である一方で、相手は裏への短く鋭いパスに適切に反応し、背後のエリアでの動きを効果的に無力化してしまう。したがってあなたは、私の足元へのパス頻度を高める必要がある。これが我々が注力すべき主要なシナジーの一例である。
あらゆる選手にとってフットボールにおける最も重要なことは、自己を完全に理解することである。選手が真に自己(自身の資質)を把握するレベルに達して初めて、チームメイトに対する深い探究を開始できる。これを習得すれば、次には対戦相手の資質を理解し、相手の資質も考慮に入れた行動選択により大きな重心が置かれるようになる。
フットボール行動を改善する初期段階では、対戦相手に関する知識はチームレベルにおけるチームの意図を定義する範囲に限定される。すなわち、選手は特定の対戦相手に対してどのように、なぜ特定のプレーを行う必要があるのかを知っているが、相手選手の資質について詳細に把握しているわけではない。こうした個別の理解に関しては、チームメイト間のシナジーも考慮に入れた特化したアプローチが必要になる。
「相手」を参照点として用いる際、アナリストが重要な役割を担う。アナリストは我々の最良の相互作用が何であるかを正確に把握しており、対戦相手に関する詳細な分析の後に、どのシナジーを用いて優位性を確立し、そこからゲームプランを構築すべきかについて明確な指針を与えることができる。実務的には、各選手に対して個別の参照型コーチングを通じて伝達すべき、いくつかの具体的な情報項目が存在するということを意味する。こうして我々は、選手が自己の資質と主要な連携間のシナジーに基づく機会に照らして、対戦相手参照に関係する効果的な意思決定を行うよう能動的に導くのである。
「我々それぞれの改善をサポートするスタッフがいる」──リバプールのMFカーティス・ジョーンズが、類似の考え方の統合について述べた言葉である。最後に指摘すべきは、戦術は選手の行動の帰結であり、したがって二次的産物にすぎず、方法論的フレームワークの出発点にはなり得ないということである。
出発点はコミュニケーション(フットボール文脈における双方向の情報交換)である。チーム全体の効率を高めたいのであれば、コーチがまず取り組むべき重要な要素はここにある。これはチームの意図を確立することによって実現される。チームレベルにおける明確な「何(チームとして次に何をすべきかという明快な問い)」を設定することが求められる。チームは我々にとって最善のアクションを正確に理解していなければならず、それこそが試合中に各選手が常に持つべき主要な思考である。
守備においては、誰が前進を妨げる者/跳び出してプレスを狙ってくる選手であるかを可能な限り効率的に識別し、その上でチームの意図に貢献するための個別の意図を選択することが重要である。攻撃においては、ボールが移動している時間に最良となる次の前進オプションをできるだけ速く、かつ効率的に認識し、チーム意図に寄与するための適切な個別意図を選ぶことが求められる。
この枠組みに関してはRaymond Verheijen氏に功績があり、彼の普遍的な参照の整備に向けた取り組みはフットボール界における明瞭性を高める助けとなるであろう。また、Rene Maric氏による「意図」と「行動」の区別を助ける研究も極めて重要であった。
◇トレーニングと状況的コーチング
我々は、コーチが説明しなくとも選手に語りかけることのできるセッションを設計できるようにスタッフ内に「セッションの設計者」を配置したいと考えている。トレーニングは、スタッフが深い観察状態にあるべき時間である。
選手に選択的知覚を備えさせ、練習そのものが選手に語りかけるようなトレーニング課題を設定すれば、トレーニングは極めて有益なものとなる。もしフィールド上を駆け回って説明ばかりしているコーチがいるならば、そのトレーニングは十分に準備されていないと判断してよい。誘発したい行動が正確に把握できていれば、トレーニングの設計は容易である──そうなれば、診断が半分以上を占めるといっても過言ではない。つまり、我々が解決しようとする問題を定義することがトレーニング設計において最も重要な要素である。
この作業はチームと協働し、選手との反省的コーチングを用いて「What’s(何をするか)」を確立することで行える。次に、演習で選手に状況を体験させるために、ゲームフェーズ・制約・暗黙的な要素・使用する選手数を定義する。
学習過程が参照型コーチングを通じて能動的に進行すれば、選手は最終的に自己の行動および他者の行動をコーチングによって最適化できる自律性に到達する。こうしたアプローチと、選手が自ら解決策を見出さなければならない状況的コーチングが存在すれば、自律的な選手が育つことは必然である。もちろん、自律的思考を持つ選手の選抜も重要な役割を果たす。これは我々がスカウティングに踏み込む際にさらに実証していく事項である。
◇共同解析
まず一言。私は、試合準備に深く没入し、その上で試合を純粋に楽しみたいと考えている。これは多くのコーチングスタッフが試合を経験するやり方とはまったく逆の姿勢である。
すべてがこれほど明確に定義されていれば、共同解析を通じて問題点を極めて正確に特定することが可能になる。本プロセスにおいて方法論と用語の整合をさらに図っていこう。私は常に、共同分析があらゆるプロセスの中で最も重要な部分であると主張しており、スタッフはそこに最も多くの時間を配分すべきだと考えている。
具体的には、1試合につき概ね8時間の実働時間が必要になるであろう。というのも我々は各アクションの原因と結果についてコメントを加え、すべてのアクションとその結論を「プログラム(我々のカスタムしたデータベース)」に蓄積するからである。
選手・チームメイト・対戦相手の映像と情報へのシームレスなアクセスを可能にし、すべての映像クリップを重要なカテゴリーごとに保存できるようにする。「選手」「ライン」「シナジー」「プレーの局面」などで整理することで、すべてを一箇所に保存し、必要なものを素早く検索できるようにする──たとえば、ある選手による試合中のすべてのアクション、あるいはハイプレスに対する攻撃といった検索である。膨大な数のアクションが蓄積され、キーワード検索(たとえば、X選手が最終ライン前の右ハーフスペースでボールを受ける)ですぐに該当箇所が出てくる。こうしたプログラムはワークフローを大幅に加速し、透明性をもたらす。
ここで我々は、アクションの成功と失敗の理由を精緻に理解し、各選手に対して評価点を与えられるようになる(各選手の評価は、その選手を担当するゲーム・インサイト・コーチが、他のゲーム・インサイト・コーチと協議の上で行う)。各アクションは個人レベルとチームレベルの双方で、不十分から最高までの評価バリエーションを用いて格付けされなければならない。そうすることで、選手がどの程度最適化されているかを我々全員が正確に把握できるようになる。速やかに基準を合わせ、個人とチームのアクションに対して同一の評価を付与し始めることが重要である。というのも、我々が意見を異にする箇所については、必ずその理由を精密に定義し、その知見をシステムに組み込み再整合しなければならないからである。
この方法を用いると、選手評価はシステム開発における最大の制約になり得る。あらゆる方法論的アプローチにはボトルネックが存在するが、その存在を認識することが重要である。したがって、特に注意を払うべきは、選手の行動の有効性と、それを導いた環境的刺激の診断である。20〜30試合を綿密に分析してそのような診断を行えば、行動パターンと選手の有効性に関する統計的に有意なサンプルが得られる。こうした部分は、偏りなく科学的かつ客観的に行う必要がある。もしこの工程が最適に遂行されれば、選手行動の最適化は真に意味のあるデータベースを土台として開始され、最終的には最大限のシナジーを創出することが目標となる。
試合には、選手がボールから遠く離れていてアクションの有効性に大きく影響を与える機会を持たない場面が多数存在する。大半のアクションにおいて、ボールから遠い選手はそのアクションの成功にとってカギではない(おおむね全体の60~70%のアクションが該当する)。
それにもかかわらず、そのようなアクションがチームの成功にとって重要である場合もある──我々は原則として、特定の選手がそのアクションに対して有意な影響をおよぼし得た場合に限り、その選手のためにそのアクションを保存する。通常、各試合後に選手一人当たりおよそ50件程度のアクションが抽出され、その中から頻度や重要性により選手の有効性に最も大きな影響を与えるものが選定される。選定されたこれらのアクション(ゲームのセグメント)に対して、ゲーム・インサイト・コーチは次週、その選手とともに取り組むことになる。
◇問題提起
一連のアクションにおいて、何人の選手が実際に、あるいは潜在的にそのアクションに有意な影響を与えた、または与えられたのかを問うべきである。
(注:個々の意図から大きく逸脱した場合ーすなわち「不十分な状態」となった場合にボールを失うという選択肢も常に考慮に入れること。)
(例:ディ・マルコが相手最終ラインの裏のファーサイドでオプションになることを認識できず、ボックス内に入るべき局面を逸した場合など)
複数の連続シーケンス(多くは10以上)を収集し、そのうち参照型コーチングに用いるために最も適した数本を選定することになる。これは、当該選手がチームの意図をどれだけ効果的に果たしたか、または果たし得たかに対して、実際にあるいは潜在的に有意な影響をおよぼした/およぼし得た場面を抽出するということである。こうした手法で数試合を分析すれば、状況の全体像ははるかに明瞭になる。基本的には1試合の分析に6~8時間を要するが、そこまで時間をかければ非常に高い水準での分析が可能である。
本件においては、ディ・マルコは「中立的な行動」を遂行した──つまり彼はボックス内でオプションとして最適な支援を提供しなかった。理由は、遠いサイドで相手最終ライン裏にあるオプションを正確に読み取れなかったためである。
私の評価は選手のそのアクションへのインパクトに基づく。ある選手が特定の行為を行った(例:ディ・マルコがボックス内で一定の支援を行った)場合、それが良好あるいは優秀な成果からは程遠いと判断されれば、中立的な評価を与える。もしその場面がより高い得点機会を生み得た状況であったならば、その選手は「不十分」に分類されたであろうが、本事例は現実的には彼がチームのボックス内でのオプションを改善することはできたものの、明確な得点機会を生む局面ではなかった、という理解である。
要約すると、我々は選手に対しその行動内に存在するアフォーダンス(行動における可能性)に即して評価を付与する。評価は選手自身の資質・チームメイトの資質・対戦相手の資質や行動を踏まえたものとする。ある行為(例:最終ライン裏のスペースを突くこと)が理論上可能であっても、選手が速度的にそれを実行できない(例:スピードが足りない)という理由だけで無条件に「不十分」と評価するのは妥当ではない。同様に、ある選手が多くの行動を継続できず、その結果としてポジティブな結果を達成できなかった場合、それはゲーム・インサイトの問題ではなくフットボール・フィットネスの問題であることを認識する必要がある。
重要なのは、重要な各アクションごとに(ここでいう重要なアクションとは、その選手が自身の行動によってチームの意図に対して有意に寄与し得た可能性がある行為を指す)「なぜその選手が寄与できなかったのか」を正確に特定することである。これが出発点であり、どの意図を、どの行動によってより良く遂行できるかを導くための分析基盤となる。
さらに試合を分析してディ・マルコに関する類似の状況を10件発見した場合、過去の行動よりも大きな影響力を発揮し得たものだけを彼のフォルダに保存するようにする。こうすることで、同一のテーマに関しては6~7件以上のファイルが保存されることを避けられる。プロセスの目的は、本質的に各選手について週単位で最も重要な1~3点のゲーム側面を改善することに還元される。これこそが我々が常に集中して取り組むべき事柄である。
選手が週に1試合をプレーする状況では、教育プロセスは試合の翌日から数えて2日目に開始するのが原則である。選手は一般的に情緒的に休息しており、新たな改善サイクルに向けた準備が整っている。重要な試合の後は、選手は試合翌3日目から新知識の習得に取り組み始めることも可能である。教育プロセスの開始日は、直近の試合の難度および次戦の近接性と難度によって決定される。トレーニング日が週に4日以上存在する週については、上記の基準に従ってプロセスを開始する。
各選手に対しては、ゲーム・インサイト・コーチが選手の週間目標(アップグレードが必要なゲームの側面)に由来する個別の参照型コーチングを実施する。改善に取り組むゲーム側面の数は主に情報の複雑性と選手の新たな知識を獲得する能力に依存する。
特殊な心理学的テストにより、各選手の知識獲得能力を評価することができ、直接的な作業を通じてその能力水準を実務的に診断し、以降の取り組みをそれに合わせて調整することが可能である。ゲームの複雑な側面を扱う場合の例として、最終ラインの開閉を読み取る技能が挙げられる。これは意思決定の際に選手が参照すべき事柄が非常に多く含まれるためである。そのようなテーマを適切に指導するには、参照型コーチングと状況的コーチングを合わせて3日間程度行う必要がある。
したがって、もしトレーニング日がさらに2日あるならば、より単純な概念も指導可能になる。例えば、攻撃フェーズにおけるファーサイドの継続的な視野確認などである。これは選手がファーサイドへ向かう斜めのパスを活用できない理由が、それらを知覚できていない点にある場合に有効である。
原則として、1回のトレーニングセッションで扱えるその種の側面は最大2点である。単純な概念は、1セッションで2つを組み合わせて指導し、翌日に反復する形が最も効果的である──この方法は、翌日の反復を伴わない「1日1項目」方式よりも知識の定着が良好であることが示されている。
学習が遅い選手に対しては、当然ながら後者(繰り返し重視)のアプローチが適している。ここに示した原則は指針として機能し、例外はその有効性を裏付ける。トレーニング日が5〜6日ある場合には、望ましい行動が定着するのに十分な時間があるため、複雑な側面を2項目、単純な側面を1〜2項目扱うことができる。
最終ラインの開閉を読み取るスキルは、知覚プロセスがはるかに複雑である。選手はほとんど全方向を観察しなければならず、その後に視覚情報を認知的に適切な方法で処理する必要がある。単にボールのパス局面における攻撃フェーズでのファーサイドへのコミュニケーション改善だけを目的とする場合と比べて、考慮すべき参照点の数は格段に多い。
また、スカウティング部門は文字通りファーストチームのスタッフの一員でなければならないことにも触れておくべきである。我々が導き出すあらゆる結論は行動として記述されるため、スカウト陣も我々が指している具体的な行動を完全に理解している必要がある(ゲームに対する、同一の言語と同一の視点で)。そのような理解水準は、関係者間で最大限の整合が達成されている場合にのみ可能である。これはプロセスが互いに融合していることによってのみ実現する。つまり、スタッフの真の統合が必要であり、全員が互いに密接に連携しているべきである。
◇参照的コーチング
私は特定のフットボールスタイルに対する嗜好は持たない。私が考えるフットボールにおける本質的な問いは次の3つだけである。
-
各選手のプレーをどのように最適化するか(参照:選手)
-
選手間で可能な限り大きなシナジーをどのように作り出すか(参照:チームメイト)
-
どのようなプレースタイルが、短期的・長期的に相手に最も高いレベルの誤認を生じさせるか(参照:相手)
以下に、ここ数週間で議論してきた事項の概略を示す。多くの内容は類似するが語義が異なるため、これまで述べてきたことを統一しようと思う。チームが効果的にコミュニケーションを図るためには、明確に定義されたチームの意図が必要である。この前提がなければ効率的なフットボールは成り立たない。なお、チームの意図は自チームおよび対戦相手の強み・弱みに応じて試合ごとに変化するものである。
以下は、単一の試合におけるチームの意図の一例である(例示)。チームの意図は、「何を行うか(What)」と「なぜそれを行うか(Why)」という問いに対して答えなければならない。例えば:
「What」右サイドでプレスを誘発し、左サイドで前進を狙う。
⇒「Why」彼らの右サイドは、プレスにおいて脆弱であるため。
「What」中央でのプレスを行い、コンパクトな距離間で中盤を塞ぐことに注力する。
⇒「Why」彼らは中央を経由したライン間でのプレーに長けている一方、最終ラインの裏に攻撃することが不得手であるため。
「What」中央での迅速な攻撃的トランジションを優先する。
⇒「Why」リスキーな中央の縦パスを狙うタイミングで、彼らの中盤の防御が脆弱であるため。
コーチは様々な方法でチームの意図を定義するが、現時点で最も精密なのはアナリストが対戦相手を徹底的に分析し、強みと弱みに基づいて試合のセットアップに必要な主要情報を要約するというアプローチである。
その後、個別の意図を定義する段階に入る。攻守において一般的に4つの汎用的な個別意図が存在することは我々の共通認識であるが、これらの各意図の出現頻度は選手の特徴──すなわち、ピッチ上の特定ゾーンでの有効性と当該ゾーンにおける選手の示す行動タイプに依存する。
ここで私はやや異なる観点に到達する。私にとって、試合における主要なコンセプトは、まず選手自身に関する知識、次に選手がチームメイトについて持つ知識であり、その後に対戦相手に関する知識が続く。後者は我々がチームの意図を通じ、間接的に伝達するものである。
我々は参照的コーチングおよび状況的コーチングを通じて選手を対戦相手に備えさせるが、同時にその焦点は選手本人とそのチームメイトに置き、彼らの効果的な行動を最適化することにある。こうしたやり方は選手に過剰な認知負荷をかけないという利点がある。なぜなら、環境に存在する多数の要因に同時によく集中することはほとんど不可能だからである。
では実践上それは何を意味するのか。リレーショナルなプレースタイルには、ギブ・アンド・ゴー(パスアンドゴー)、ダイアゴナルプレー(斜めのプレー)といった概念が含まれる。これらはすべてチーム内のコミュニケーションとそこに包含される個別の意図を生み出すための用語だが、私はこれらの概念を選手個人を中心に据えて構築したいと考えている。
説明はダイアゴナルプレーから始めよう。この概念を理解する過程で、選手はフィールド上のアフォーダンスを認識する──たとえば周辺に複数の選手が斜めに並ぶ状況を捉え、その状況で当該概念を遂行する、といったことである。このように定義された概念は、選手がチームの状況を読み取り、共通言語を形成することを容易にする。だが、この種の概念には限界があり、私がそれをチーム意図を作るための補助的手段に留めている理由は、それが選手個々の個別概念について何も教えてくれない点にある。
たとえば、3人によるダイアゴナルプレーの中であなたが第1の選手であるならば、あなたもチームメイトも各々の最適な行動を知らなければならない。私が狭い空間(2~3メートル)でボールを受けるプレーを苦手とする選手であるなら、私の主要な意図は相手の最終ラインの裏を攻めることであり、その結果として味方のオプションになったり、チームメイトのために相手最終ラインの前後にスペースを生み出したりするだろう。
あるいは私がカウンタームーブメントの専門家であるかもしれない。そうした選手は、スペースのない状況から時間とスペースを創出し、もともとボールを受ける資質を欠く局面でも受けられる状況を作り出す。あるいは、スペース自体を必要としないタイプであって、そのような状況を利用して優位性を作る選手である可能性もある。要点は、選手こそが最も重要な概念であるということである。
選手がシナジー効果を生むよう構造化され、各対戦相手に対して明確に定義されたチームの意図を持ち、かつ自己とチームメイトに関する十分な知識を備えているならば、我々はその環境下での潜在能力を最大化しているといえる。なぜベリンガムは、バルベルデが外のレーンでボールを受けた時に裏を狙ったのか?それは彼が裏へのパスを狙うことを好むバルベルデの特性を理解していたからだ。
私はまず第一に、そうした方法こそがチームにアイデンティティと統一的思考を与えるチーム言語の創出だと考えている。スタッフの役割は、選手とその行動をより詳細に理解し、それらを可能な限り少数のコンセプトで同期させて、選手間で発生し得る多数のシナジー的相互作用を説明できるようにすることである。
もし私が右センターバックで、あなたが守備的ミッドフィールダーであるならば、私はあなたの特性に適した方法でプレーする術を知らなければならない。すなわち、あなたが効果的に機能するあらゆるアクションにおいて、どのようにボールを扱うべきかを理解しておく必要がある。どの状況でどちらの足にパスを出すべきか、どの速度で、どの方向にボールを出すべきかを理解することで、チームメイトに適した次のアクションを誘発できる。
たとえば、あなたは私がボールをキープするのが苦手であることを知っているが、私は左側へのワンタッチパスを得意としている(右利きであるため)。したがって、あなたは私にあえてゆっくりとしたボールを送ることで、そのアクションを実行せざるを得ない状況を作り出す。また、私が右方向よりも左方向へのドリブル能力が高いと知っていれば、あなたは左方向へのドリブル状況を生み出すパスを出す。あるいは、私が右サイドとのコミュニケーションを得意としていることを知っていれば、あなたはその方向へのパスをより多く出すだろう。なぜなら、あなたは私がその後、味方にボールを渡した後にアクションを適切にサポートできると理解しているからだ。私はまた、あなたが相手の勢いを利用する能力に優れていることを知っているため、私はあなたが相手に勢いよく詰め寄られている瞬間に届くようなパスを出す。
例を挙げればきりがないが、ここでは私が言わんとしていることを明確にするためにいくつかの事例を示したに過ぎない。チームメイトを知ることは、フットボールにおける最も重要な外的概念である。我々がここで扱っているのは、選手が明示的にも暗黙的にも徐々に獲得すべき膨大な知識量であり、これは極めて体系的な学習プロセスを要するものである。しかし現状のフットボール界は、この側面において選手を最適に支援しているとは言い難い。
明らかなこととして、選手はこれらの知識のうち一部を明示的に理解しておけばよく、残りの多くはチームメイトとの多数の相互作用を通じて潜在的に理解されるものである。指導者はまず、試合中に最も頻繁に現れる、あるいは試合結果に大きく影響し得るチームメイトに関する明示的情報を選手に伝達することが重要である。情報伝達の優先順位がこのように設定され、さらに暗黙的トレーニングがこうした状況を最大限に多く再現できるよう設計されれば、選手は徐々に状況的効率性を最適化し、この知識は潜在化し、行動は無意識的効率へと移行していくことになる。
これらすべての知識は非言語的コミュニケーションの改善に関係しているが、これに加えて言語的コミュニケーションも個別に最適化される必要がある。すなわち、我々は試合中の指示についても明確な言語的シグナルを設定している(例:前後、左、右、プレス)。しかし同時に、選手間には独自の言語が存在する。たとえば、私があなたにパスを出し、スルーパスのコースが開いている場合、私は「(XYZ)」と声をかける。このような言語的コミュニケーションは、一定の範囲までは選手間で自然に発展するものであり、指導者はその形成を導き、支援する立場にある。
もし我々がこのような方法でチームを構築できれば、そのチームは非常に高度なコミュニケーション言語を備えることになるだろう。すなわち、チームとして真に一体感を持ち、深いアイデンティティを形成するのである。
──もしここまで読み進めたのなら、あなたは私たちと同じように、狂気的なまでにフットボールに情熱を持つ人間であることだろう。
文:ヤニス・サラシディス(@Yiannis_Tsala)
〈プロフィール〉大学生時代にカナダ3部でプレーする傍らで、指導者としてのキャリアをスタートした若手指導者。グラスルーツからアカデミーまで幅広いレベルで指導経験を重ね、レッド・リバー大学ではアナリストとしても活躍。その後は地域のサッカー協会のコーディネーターなどを経て、2019年にU-17カナダ代表の強化合宿でコーチを担当。同年のフランス女子W杯ではカナダ女子代表のアナリストとして活躍した。その才能を評価され、2025年にはスロベニアリーグのNKドムジャレでもアシスタントコーチを経験した。現在は、本記事にもある「ゲーム・インサイト・コーチング」というコーチング思想を広めながら、個人分析などでもチームをサポートしている。
ゴラン・ロサンダ
〈プロフィール〉UEFA A ライセンスを保持する、36歳のクロアチア人コーチ。ユース世代の指導からステップアップに成功し、HNKハイドゥク・スプリトやクロアチアU19代表でもアシスタントコーチを経験している。
Kannan
〈プロフィール〉匿名で活動中のアナリスト/スカウト
Meia Armador (@MeiaArmador__)
〈プロフィール〉匿名で活動中のプロコーチ/スカウト
訳:結城康平(@yuukikouhei)
ディ アハト第106回「ゲーム・インサイト・コーチの日誌」、お楽しみいただけましたか?
記事の感想については、XなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!
ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら