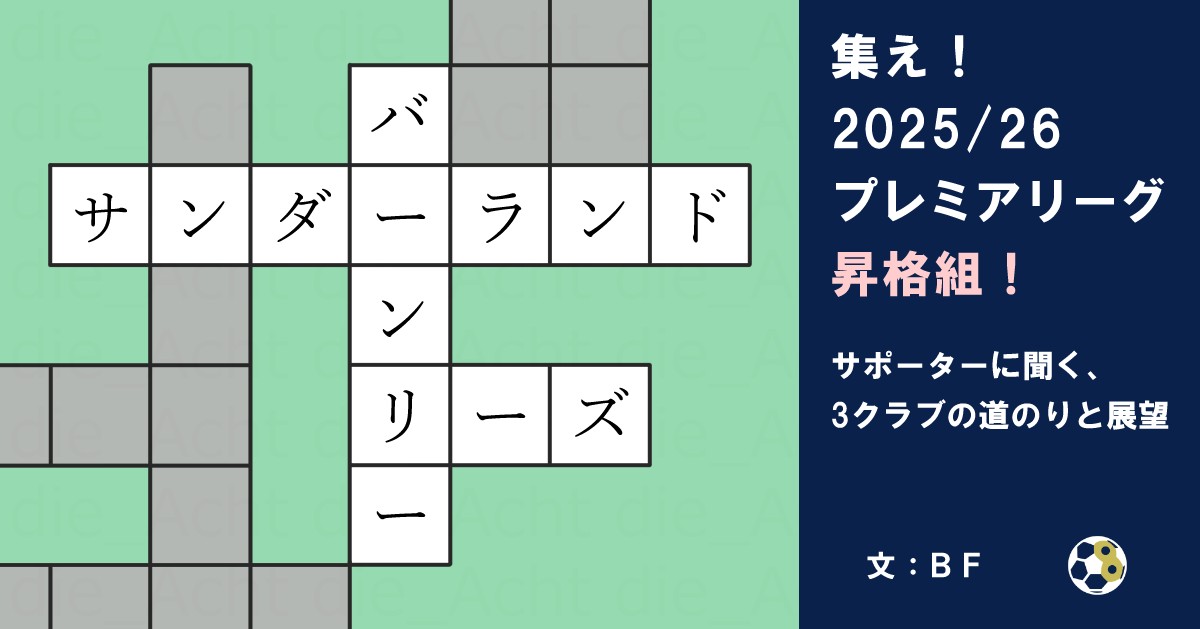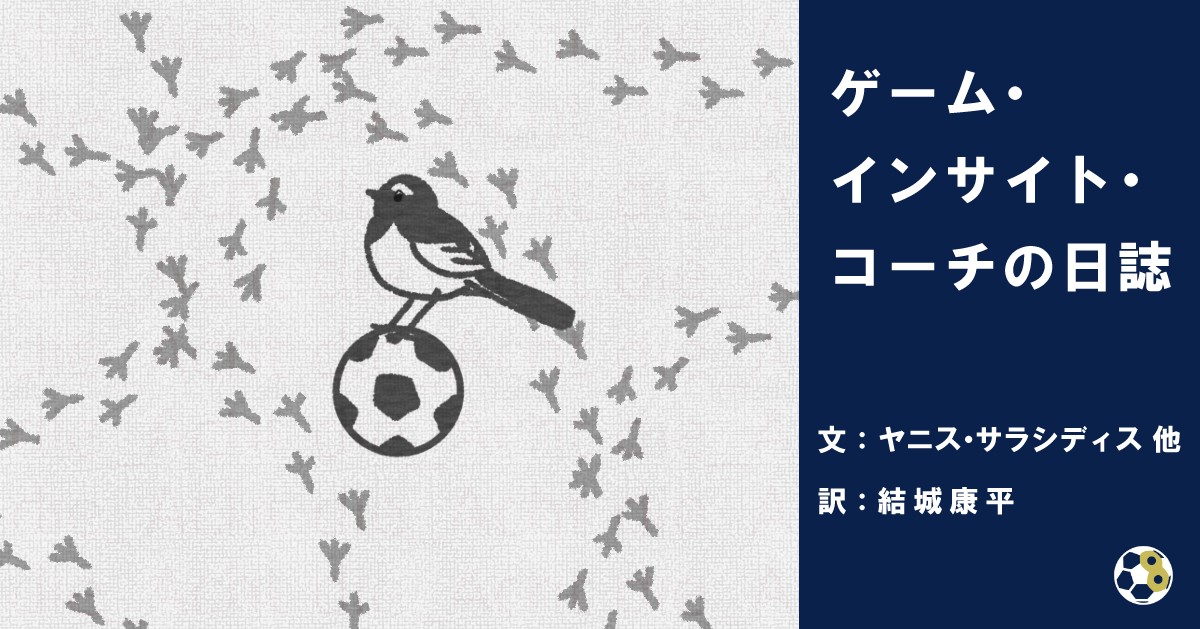総括 東京2020五輪【チーム・強化編】

こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第14回は、東京五輪総括のチーム・強化編をお届けします。オリンピックを振り返りながらぜひご一読ください!
また、購読登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事を見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。
昨日配信させて頂きました、第13回の「総括 東京2020五輪【選手編】」もご一緒にお楽しみください。そちらにも多くの感想を頂いており、とても嬉しく思っております。
◇「4-4-2ブロック」に依存した守備が抱えていた、潜在的なリスク

news.livedoor.com/lite/article_d…
スペイン戦から先発2名を変更し、冨安健洋と相馬勇紀がスタメンに復帰。53年ぶりの銅メダルを懸け、メキシコとの大一番に臨む。
それでは、今大会の日本代表を守備の局面から考えていこう。森保監督は、オーソドックスな4-2-3-1をチームの主なフォーメーションに選択。DFラインにはオーバーエイジの吉田と酒井が絶対的な主軸としてプレーし、左サイドバックは中山が最終的にレギュラーポジションを掴んだ。吉田の相方として期待された冨安は怪我の影響もあり、その穴を板倉が埋めることになる。守備的な中盤は遠藤航、田中碧が絶対的なレギュラー。攻撃的な中盤に久保と堂安が固定されており、日替わりだったのは左サイドハーフ。前線には、1トップで林が起用された。
相手がボールを保持した場合、日本代表の守備はフラットな4-4-2ゾーンがベース。このやり方に選手が慣れており、比較的チームとして選択しやすかったのは事実だろう。両サイドハーフは守備ブロックの一員となり、前線2枚が比較的自由に相手のビルドアップ阻害を任される。主に相手のセンターバックに林が圧力を強め、アンカーのポジションをトップ下の久保がカバーする。
ただし、この2枚の役割も選手の裁量に任せる部分が大きかった。完全に久保が相手のアンカーにマンツーマンという訳でもなく、決まったラインを越えると中盤にスイッチ。相手のセンターバックに久保がプレッシングを狙う場面も多く、チームの攻撃が終わった状態によって右サイドの堂安が中央に残ることもあった。しかし、堂安が中央に残った局面ではハイプレッシングの意識が強く、結果的に中盤の守備が手薄になっていたことにも言及すべきだろう。
堅実な4-4-2において、日本代表の核となったのはボールを奪取する能力に長けた遠藤だ。彼が中央に蓋をするだけでなく中盤を制圧することで、本来は危険なエリアである中央で攻守を反転。センターバックも安定していたので、相手をサイドに追い込んでしまえば本職センターバックの中山と酒井が対人でウイングを抑える。この理想的な守備が成功したのが、グループリーグ「メキシコ戦の前半」だろう。中山が相手のエースであるディエゴ・ライネスを自由にさせず、逆サイドでは酒井が相手WGを完封。こうなってくると、遠藤と田中のプレッシャーでボールを奪える場面が増えてくる。
ここで最大の問題となったのは、両サイドハーフの守備で「どのラインから相手のサイドバックに寄せるか」という部分だ。4-4-2が崩される最も典型的なパターンの1つが、両サイドの選手を誘い出されて「DFライン4枚-守備的MF2枚」だけで守らなければならなくなることだ。日本代表は相馬と堂安が高い位置からボールを奪おうと飛び出していくことが多く、結果的に「前の4枚」と「後ろの6枚」が分断される事象が発生。こうなってしまうと、相手チームとしてはサイドのエリアから数的優位を作りやすい。
メキシコも初戦から日本の脆さに気付いており、後半はセンターバックが外に流れるプレーとサイドバックが低い位置で受けるプレーを積極的に仕掛けていく。結果的にサイドに起点を作られ、スペースを使われる場面が目立った。相馬と堂安、久保は日本の育成が「積極的なプレッシング」を重要視している中で育ってきたことを感じられるような「出足のスピード」で守備を牽引しようとしたが、連動しないことで相手にスペースを与えてしまった。同時に前の4枚と後ろの6枚が分断されたことで、相手チームの波状攻撃を浴びることになる。そこを必死に走り回る林がカバーしていたが、下記の指摘通り「そもそもセンターフォワードが相手を追い回さなければならない構造」自体を問題視しなければならないはずだ。

終盤、左のアタッカーとして旗手が重宝されたのは攻撃でのバリエーションに加えて「守備時にブロックまで戻る意識が高く、釣り出されることが比較的少ない」という強みを評価されたこともあったのだろう。しかし、それも個人の努力だけではどうしようもない部分だったのは残酷だ。
林もプレッシングが直線的で、相手のビルドアップを阻害しきれない場面が目立った。それでも献身的に走り続け、パウ・トーレスでさえも林の執拗なプレッシングを嫌がっていたのも事実。そういった技術面・戦術面では、まだまだ彼のプレッシングにも伸びしろがありそうだ。効率性を増せば、攻撃に使う体力も残して置ける。そうなればゴール前で、今よりも危険な選手に変貌することになるだろう。

HALF TIME
16 #相馬勇紀 ⏩ 13 #旗手怜央
🏆#Tokyo2020 3位決定戦
🇯🇵#U24日本代表 0-2 U-24メキシコ代表🇲🇽
⌚️18:00KO※20:00より変更
📺NHK Eテレにて放送中
🔗jfa.jp/national_team/…
#jfa #daihyo
#サッカー 男子:日程・結果|第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 第32回オリンピック競技大会(2020/東京)の男子:日程・結果ページです。 www.jfa.jp
例えばニュージーランドやスペインの狙いは、セントラルハーフを置くことで「サイドでの数的優位」を担保することだった。特にニュージーランドの指揮官は聡明で、見事にゲーム中の変更で4-4-2ブロックを攻略。久保や堂安を有する日本を相手に中盤の守備力を削る「中盤ダイヤモンド」は、勝負の一手として見事に成立していた。

【以下のイタリックの部分は、ニュージーランド戦マッチレビューの内容を再掲しております。覚えている方は、読み飛ばしていただければ幸いです。】
ニュージーランドが「攻略の糸口」としたのが、日本のサイドハーフとボランチの間に生まれるスペースだ。彼らは中盤をダイヤモンドの配置にすることで、中央で「3 vs 2」の数的優位を創出。カラム・マコワットはトップ下とウイングのポジションを献身的に走り回り、攻撃をサポートしていく。結果的に中央のウッドとマコワットを警戒した中盤2人はセントラルハーフを捕まえられず、「サイドハーフ個人の頑張りに依存する状況」になってしまった。それでも堂安が何度か懸命に戻る場面があったが、個々の努力だけでは限界がある。このフォーメーションチェンジで、日本は完全にペースを握られてしまうことになる。
副次的な効果として、セントラルハーフの位置にボールが収まるようになったことで両サイドバックも高い位置に進出。結果的に最も怖い選手の1人である、左サイドバックのリベラト・カカーチェ(20歳、シント=トロイデンVV)が攻撃参加する回数も増えていく。

更に、冷静になったニュージーランドは日本のサイドハーフを前に誘い出して「セントラルハーフが外に流れてボールを受ける」ようなパターンも活用。日本は完全にペースを握られてしまい、明確な解決策を見つけられないまま延長戦に突入することになってしまう。
このようにサイドハーフと前線からの守備に大きな問題を抱えていた日本代表。難しいのが4-4-2という守備システム自体も「構築しやすいが、攻略されやすい」ものになりつつあることだ。
現代フットボールでは、既に4-4-2の攻略法が出回ってしまっていることから、EURO2020では5バックが流行。アトレティコ・マドリードの指揮官ディエゴ・シメオネのように徹底して鍛えなければ、4-4-2ブロックで強者を苦しめるのは難しい。もちろん配置だけでずべてが決まる訳ではないが、育成年代も含めてどのようなシステムに慣れさせるかは1つのポイントになるのではないだろうか。例えばベルギーやオランダは育成年代の基礎として4-3-3でプレーさせており、A代表への適応もスムーズになっている。
遠藤という「例外的な守備力のMF」と田中という「バランス感覚に優れたオールラウンダー」が偶然にも揃っていたことで「中盤2枚」での守備が成立していたが、近年は「中央を2枚で守ること」も難しいという主張も存在する。レアル・マドリードがモドリッチとクロースの後ろにカゼミーロを置いたのは印象的で、例えば所属チームのように遠藤が中盤の底を支え、その前に2人のMFを配置するフォーメーションを検討する余地もあるはずだ。
本来はトップ下というポジション自体も存在しないチームが多い今、久保は今後セントラルハーフやサイドハーフ、場合によっては0トップとして前線でプレーするなど、プレーの幅を広げていく必要があるだろう。その流れを考えても、代表チームで「4-4-2(攻撃時は4-2-3-1)」に固執する必要はないようにも思えてならない。
また、4-4-2という守備ブロック自体がマッチアップをベースにしており「個の能力」に依存しやすい。3バック(5バック)が好まれるのは最終ラインで数的な優位を保ちやすく、スペースを狭くすることで個の能力差を埋められるというシンプルな要因も大きい。例えば今は遠藤や吉田、酒井、冨安の存在が4-4-2を成立させているかもしれない。それを今後、続けていくのかには一考の余地がありそうだ。
逆に4-4-2のブロックに今後も頼っていくのであれば、サイドハーフを目指す選手にはブロックを構築する守備能力を求めていく必要がある。中央に絞ることを厭わない姿勢も含めて、堂安はスペイン戦で予想外の「適正」を示したが、この役割は恐らく久保や三苫、相馬には難しいだろう。当然、そのようなサッカーを目指していくのであれば育成年代から選手に求める要素を調整していく必要がある。例えば前田の守備範囲は、そういったサッカーをするとなれば魅力的なものになっていく。結局、どのようなサッカーを目指すかによって必要とされる選手も大きく変わっていくというだけの話なのだろう。
◇解決されなかった、ビルドアップの課題
「ボール保持をする時間が少なく、終盤で疲労困憊になってしまった」、というのは大会後に選手が語った「反省点の1つ」だ。しかし、配置自体が4バックで固定されていたことを考えるとビルドアップのルート自体が不明瞭になっていたことが、根本的な原因であることまでは深掘りされていないように思える。
結局メキシコとの3位決定戦でも、吉田の横からプレッシングを狙われ、酒井のところで袋小路になったところで縦パスを回収、そこからショートカウンターで容赦なく刺されているのだ。「ボールを保持して、体力を温存したい!」と言えば、相手がボールを保持させてくれる訳ではない。結局、どのようにボールを循環させるルートを作っていくのか、というコーチングチームに課せられた課題は最終的に解決していなかったように感じられた。
例えば所属チームでも取り組んでいるパターンをベースにするのであれば、遠藤はドイツでDFの間に下がっていく「サリーダ・ラボルピアーナ」のビルドアップを経験している。彼自身も相手が対策を練ってきたことで、狭いスペースに追い込まれてしまう場面が目立っていたので「DFラインまで下げる」ことでプレッシャーを軽減することは1案だったはずだ。
同時にサイドバックも高い位置に上げたいのだが、ここでネックとなるのが守備的な構成として中山を左サイドバックに起用したことだ。左サイドバックの位置が低くビルドアップへの参加が少ないことで、相手チームが右サイドを狙う展開になりやすかったのは悩ましい部分だった。だからこそ旗手をサイドバックで起用するという構成に、指揮官も期待していたのだろう。そういう狙いを相手が持っているのであれば、例えば田中や遠藤を左右サイドバックの位置に流しながら、相手と駆け引きするのも一案となる。これはリバプールでヘンダーソンやワイナルダムが得意としているメカニズムだが、サイドバックを押し上げることで相手に「どのように対応するか?」を尋ねていく。
結局、後述する内容とも関連するのだが「フラットな状況から相手の狙いを確認し、それに合わせて駆け引きしながらプレーする」というようなプレーを日本代表は伝統的に苦手としている。将棋では「含みを持たせる手」という言葉があり、これは複数の戦型に対応可能な手を選ぶことで相手を牽制することを意味する。日本代表は用意している策を決め打ちしており、戦術の変化は主として「選手の変更」に頼ってしまっているのが実状だ。ポジションチェンジも中盤の可変で駆け引きしながらの仕掛けではなく、あくまでインスピレーションをベースにしているので他の選手が連動しきれないことが多い。
◇強豪国との対戦で明らかになった「高い壁」の正体とは?
チームにおいて絶対的な存在でありながら、その課題を明確に言語化していく。今大会でパフォーマンスだけでなく、選手としての大局観も感じさせた田中の将来は明るい。エースとして君臨した選手たちが「俺が決めていれば」と個人の課題として大会を振り返ることが多かった一方、彼はあくまで「相手チーム」をベースに差を言語化している。もう聞き飽きたかもしれないが、田中碧のような聡明な選手を育てた川崎フロンターレという環境への興味は尽きない。
「個人個人でみれば別にやられるシーンというのはない。でも、2対2や3対3になるときに相手はパワーアップする。でも、自分たちは変わらない。コンビネーションという一言で終わるのか、文化なのかそれはわからないが、やっぱりサッカーを知らなすぎるというか。僕らが。彼らはサッカーを知っているけど、僕らは1対1をし続けている。そこが大きな差なのかな」
似たことを、名伯楽イビチャ・オシムもメディアに語っている。
メディアにとって彼のような選手は扱いやすいだろうが、忘れてならないのはサッカーはコレクティブな競技であることだ。個のプレーが行き詰まったときに勝つのはコレクティブだ。それが今日の試合でよくわかったはずだ。スペインがそれを証明した。サッカーに限らず私が見るすべてのスポーツで、スペインの第一の目的は試合に勝つことだ。どんなやり方であろうと勝つ。内容がどうであれ、勝つためにすべてを尽くす。大事なことはそこにある。常に勝者であろうとすることだ。
では、田中とオシムが指摘する「コンビネーション」や「コレクティブ」というのは何なのだろうか?その疑問に答えるには、スペインのフットボールが最高の教材だろう。彼らのコレクティブは、スペースをどのように分割するかという思想で成り立っている。それは、ホールケーキを友達と食べるときと一緒だ。彼らは常にピッチ上の状況を認知しながら、相手と自分たちがどのようにスペースを占有しているのかを確認している。そこで、スペインと日本が違うのは「味方にスペースを使わせる」という意識だ。
スペースを誰が使うのか?どのように入れ替わるのか?スペースを閉じてしまった選手は、どのように囮になるのか?この意識が日本とスペインの差として現れた最大の差であり、これはオフザボールでの連動やコミュニケーションの頻度からも明確だった。
日本人選手にも、当然「周りを使おう」という意識はある。しかし、それはあくまで「自分がボールを受けること」の先にあることでしかない。例えば久保は認知能力が高く、ドリブルしながら周りの選手へのアシストも狙っていける。ただ、それはあくまで「ボールを受けてから」の仕掛けだ。
自分がボールを受ける動きが失敗したときに、数歩ダッシュすることで他の選手を助けるサポートをしよう!というところまでは意識が行き届いていないのだ。当然、誰の動きを助けるのか?というところもイメージ出来ていない。これが、田中が語った「2対2や3対3になるときに相手はパワーアップする」という言葉の正体である。
そして、この差が結果的にボール保持者の「スペースを使う選択肢」を加速度的に増大させる。それがスペインの選手が巧く見える「最大の秘訣」なのだ。スペインのMFはテクニックを武器にしているが、日本のMFも決して劣ってはいない。それでも「スペインの選手からボールを奪うのが不可能に感じられる」のは「選択肢を多く与えられているから」に他ならない。連動のタイミングでスペインはボールを受ける選手を変えるので、結果的にパスを出す側がどのタイミングでボールを供給するかで、描ける絵は一変する。
これはある意味で、日本人選手が海外で「助っ人」として活躍していることの弊害でもある。結果を求めていけば、当然ボールを受ける回数を増やしたい。野球で考えれば、どんどんと大振りになっていく訳だ。それでもホームランが増えてくれば、周りの選手がバントや盗塁でサポートしてくれるようになっていくだろう。日本の選手たちは主軸のホームランバッターとして活躍する選手が多く、結果的に打線が大味になってしまっているのだ。他のスポーツでも普通に起こりそうな事象である。
最後に、スペインと日本の差を実感させた印象的なプレーの1つで今回の総括を締めくくることにしよう。それが、エリック・ガルシアとパウ・トーレスの1プレーだ。相方のパウ・トーレスを林がマンツーマン気味で抑えようとした時間帯、右CBのガルシアは数回あえてパウ・トーレス側にドリブルすることで、林の挙動を観察した。そこで左CBのパウ・トーレスは林がガルシア側に移動しないことを確認すると、あえて少し外に移動。林をガルシアから遠ざけつつ、あえて自分が死ぬことで「ガルシアのスペースと時間」を作る選択をする。結果、ガルシアのところから正確なパスが供給されたことで林に迷いが生じるようになっていく。
このように自然に「チームメイトのために自分が死ぬ」トーレスの選択と、「林の意図を探りながら、次のプレーを考える」ガルシアの選択。このような連携を見せられると、サッカーの深遠さを感じるのだ。
東京での挑戦は終わり、新たなシーズンが眼前に迫っている。選手たちは再び次の目標に向かっていくだろう。日本が真の強豪国になっていく過程は、長く険しい。しかし、その過程を楽しむことこそが我々ファンに与えられた最高の贅沢なのだ。
文:結城康平(@yuukikouhei)
ディ アハト第14回「総括 東京2020五輪【チーム・強化編】」、お楽しみいただけましたか?
記事の感想については、TwitterなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!
ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら