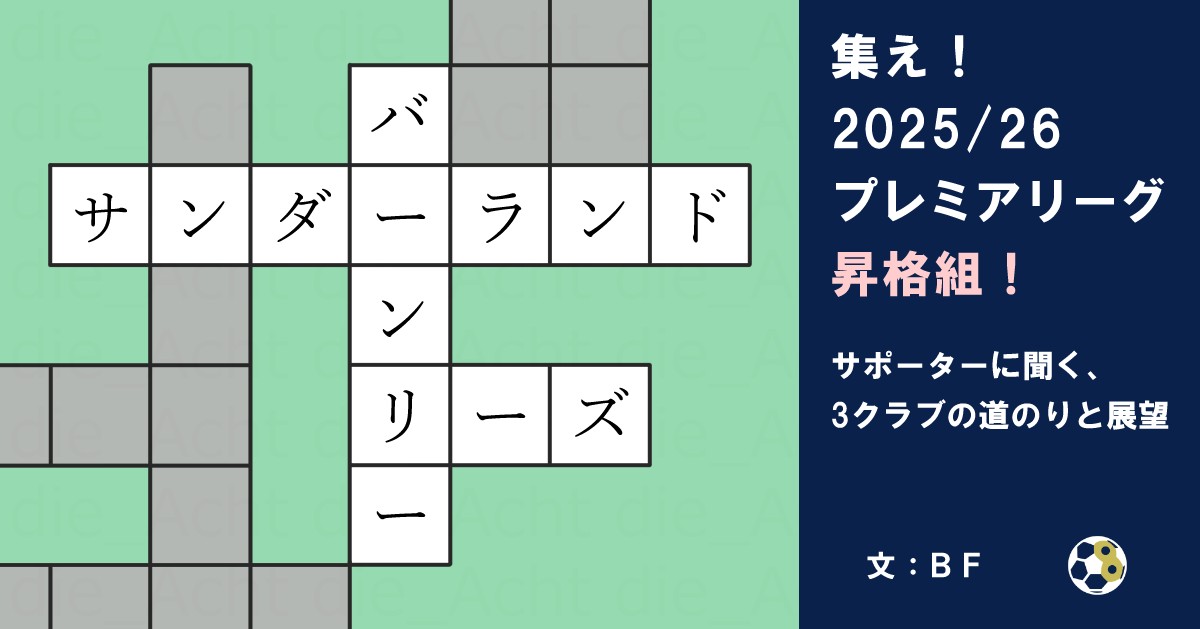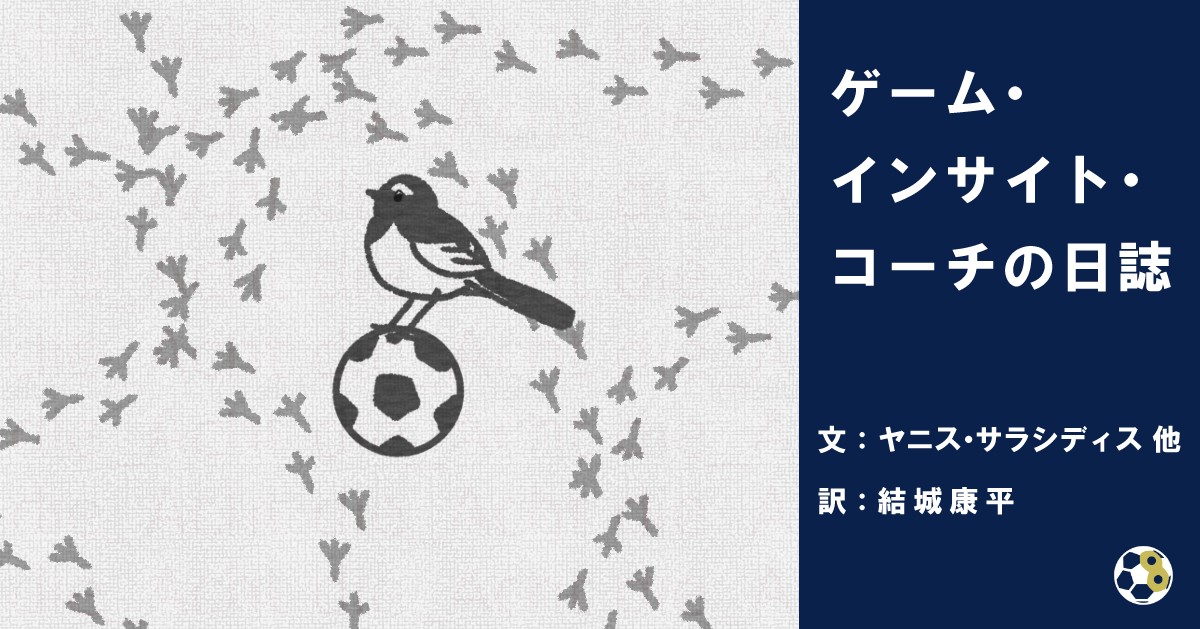チーム分析:トッテナム / ジャンニ・ヴィオ[セットプレー]

こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第80回は、22/23シーズン第5節までのトッテナムのセットプレーを白水優樹(@shiroe___s)氏が分析した記事をお届けします。今季から新たにセットプレーコーチが加入した同チーム。どのようなデザインがなされるのでしょうか?ぜひお楽しみください!
また、購読登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事や限定コンテンツを見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。
◇はじめに
今回は、セットプレーコーチ「ジャンニ・ヴィオ」を迎えたトッテナム・ホットスパーのセットプレー戦術を分析していく。

squawka.com/en/tottenham-g… Spurs confirm Gianni Vio has joined Antonio Conte's coaching staff as ‘the little wizard’ looks to fix one glaring weakness Antonio Conte has continued his summer of spending by recrui www.squawka.com
ヴィオは、ACミランやリーズ・ユナイテッドでセットプレーを専門に扱うコーチを務めた経歴の持ち主で、EURO2020ではイタリア代表の優勝にも貢献。元銀行員でありながら書籍や論文を通して自身のセットプレーにおける理論を発表し、黎明期に「セットプレー専門コーチ」という役職を確立した人物の1人としても知られている。
本稿では、トッテナムの今季22/23の開幕からウエスト・ハム戦までの5試合におけるセットプレーの分析と考察を通して、ヴィオがどのような狙いを持ちトッテナムのセットプレーをデザインしているのかを考えていきたい。
筆者個人としては、「ニア」「パターンの固定化」「ファー詰め」「ボックス外のマネジメント」の4つがトッテナムのセットプレーにおいて重要なテーマであると感じている。はじめに、CKの攻撃戦術から分析していく。

More information ⤵️
◇コーナーキック:攻撃
コーナーキック(CK)の攻撃における狙いは、対戦相手の守備に応じて変わる。そのため、それぞれの試合においていくつか例を上げながら見ていきたい。
・第1節 vsサウサンプトン
まずは第1節のサウサンプトン戦について、トッテナムの基本的な情報を以下にまとめていく。
キッカーを務めるのは基本的に右利きのソン・フンミンで、右からはアウトスイング、左からはインスイングの軌道でボールを入れる。クルゼフスキがボールを拾ってボールをセットすることがあるが、その場合は素早くショートコーナーで再開される。そのため、セットされた状態でのCKは基本的にソン・フンミンが担当すると言える。
このように左右でインスイング・アウトスイングと球種が変わる場合、それに応じて中の動きのパターンが変わることが多い。実際トッテナムは、インスイングとアウトスイングとではセットの仕方を変えている。
まずは、アウトスイングのCKから見ていく。なお、サウサンプトンは全員がゾーンで守っていた。

図1:第1節サウサンプトン戦におけるCKの動き(攻撃側)1
図1は、前半4分のCKにおける選手の動きとボールの軌道を表している。
まずアウトスイングという特徴を踏まえると、攻撃側の選手に向かってくるボールに対して勢いを持って飛び込むというアプローチは非常に効果的だ。そのため、トッテナムも中の選手はPKスポットよりも後方からスタートしている。
興味深いのが、図1に示すように彼らは3人と4人のグループに分かれ計7人がボックス内にポジションを取り、ペナルティアーク付近でセカンドボールを回収する選手を最初の時点で置いていない点だ。
そしてキッカーのソンが手を上げた段階で、3人(19番・5番・21番)の選手がボックス外に出ることでセカンドボールに備えたポジションを確保し、彼らが移動を終えそうな段階でソンは助走を取りボールを入れる。この動きのメリットとしては、守備側に誰が飛び込んでくるのかわからない状態を作れることや、マンマークの相手に対しては「攻撃の起点として、エリアの外でセカンドボールを回収する選手」*を置かせないように牽制できることが考えられる。
*最初からエリアの外に選手を置いておくと、マンツーマンで相手もその付近に選手を配置する。その選手が攻撃の起点になる可能性があるが、トッテナムのアプローチはそのリスクを軽減する効果がある。
実際、毎回同じ選手が同じ流れで動くので、ピッチ外から見ているとそこまで効果はなさそうな気もするが、それは実際に守備側の目線にならないとわからないところだ。ちなみに、ショートコーナーのオプションを用意するためにサイドに立っている選手(この図では21番のクルゼフスキ)が図1の矢印の形で中に戻らなかった場合、彼をマークしている相手選手が内側のレーンをカウンターで走ることができてしまうので、これはどのチームでも大切な動きとなる。
さて、CKの狙いとしてトッテナムは「ニア」を徹底的に狙っている。これはこの試合に限らず、第5節までの段階では毎回ニアを狙う。ターゲットになるのは15番のダイアーであることが多く、1人が一番手前側の守備者を引っ張り出し、開けたスペースにダイアーが飛び込んでくるという形が多い。

図2:第1節サウサンプトン戦におけるCKの動き(攻撃側)2
図2のように、1人が相手の前に入るとほとんどの場合ニアを守る選手は釣られて前に出てくる。そうなるとゾーンで守る相手に「繋がり」がなくなり、わずかだがスペースを広げることができる。そこにターゲットとなる選手を飛び込ませよう、というのがトッテナムの狙いだ。
次は、インスイングのCKでの配置と狙いを見ていく。

図3:第1節サウサンプトン戦におけるCKの動き(攻撃側)3
図3は前半31分のCKのシーンで、セカンドボール回収からの三次攻撃でダイアーが逆転ゴールを奪っている。
CK自体の狙いとしては、「ニアを狙う」という点は変わらない。ただし、ボールの軌道の変化によって初期配置にも変化が加わっている。アウトスイングに対しては、ボールがゴールから離れるような軌道になるのでゴールに向かって走り込みながら合わせていたが、インスイングの場合はゴールに向かってくるボールになるので、軽くフリックするだけでもゴールになりやすい。
また、ゾーンで守る相手に対しては背後から現れることで、相手よりも先にボールに触りやすくなる。そのため、相手GK周辺からニアに向かって走り込み、インスイングのボールをフリックするための配置と動きになるのだろう。
一方、7人の選手をボックス内に送り込んで3人と4人に分けるところや、3人がキックの前にセカンドボールに備えたポジションを取るところはアウトスイング時もインスイング時も変わらない。
ここまで、トッテナムのCKにおけるベースとなる狙いについてまとめた。ここからは、より各チームごとへの対策といったところにフォーカスしていきたい。
・第2節 vsチェルシー
先ほどキッカーは「基本的に」ソン・フンミンと書いたが、相手チームにとって厄介なのが左利きではあるが「右足でも高い精度で蹴れる」ペリシッチだ。
この第2節の試合では、トッテナムはペリシッチ投入後にインスイングを狙うために左サイドのCKやFKは右足でボールを入れるようになった。また、キックの種類を固定するだけでなく、動きのパターンも固定されていた。そして、結果として後半アディショナルタイムでの同点弾に繋がる。

図4:第2節チェルシー戦におけるCKの動き(攻撃側)1
図4は、ケインのゴールにつながったCKの流れを示す。
チェルシーの守備は、5人がゴールエリアをゾーンで守ることと、ダイアーへのマンマークが特徴だ。あくまでもゴールエリアはゾーンで守られているため、ダイアーや33番のデイビスはそのゾーンの中からニアに出てくる動きでボールに合わせようとする。ここでフリックしてゴールという形も十分に考えられるが、ゴールに繋がったのはもうひとつ奥のエリアだ。

図5:第2節チェルシー戦におけるCKの動き(攻撃側)2
ダイアーとデイビスがニアに流れチェルシーの4人の選手を引きつけることで、ゾーンで守る選手同士の「繋がり」を断ち切る。また、中央のクリバリがゴールカバーに入ったこともあり中央にスペースが生まれ、ケインだけでなくリシャーリソンやモウラもフリーで合わせられるような状況になっていた。
この試合を通じて、トッテナムはケインをゴール前中央に残し、ダイアーとデイビスでニアを狙うというパターンを使い続けており、最終的に中央のケインでゴールを奪うことができた。しかし、キッカーが狙うポイントとしてはケインのところではなく、ニアのダイアーを狙うシーンも多かった。これは、トッテナムは同じ動きのパターンから2ヶ所の狙いを持っていたとも考えられる。もしくは本命は中央のケインだが、単純にボールがニアをなかなか越えられなかったのかもしれない。
CK分析の難しいところでもあるが、「実際に蹴ったところ=キッカーが本当に狙っていたところなのかどうか」はピッチ外で見ている我々にはわからない。それでも、ニアでフリックできるし中央にもスペースを作れるといったように、1つのパターンの中に複数の狙いを持っておくことは重要だろう。
実際、トッテナムは同じ試合の中では基本的に同じ動きを続けることが多く、またキッカーはニアで合わせるボールを狙い続けていた。色々なパターンで相手を惑わすことも1つの狙いではあるが、トッテナムはむしろ「相手の弱点を突ける1つのパターン」を執拗に狙い続けているのではないかと思われる。少なくともこのチェルシー戦は、最終的にそれが報われた試合となった。
・第3節 vsウルヴァーハンプトン
ウルヴァーハンプトン戦は、最初の1本はアウトスイングだったものの、その後はソンとペリシッチがインスイングを採用した。対する相手守備はマンマークをベースにしていたが、ニアは2人がスペースを守っていた。
マンマークで守るとはいえ、多くのチームはニアでスペースを守る選手を置いている。そのためニアの使い方はゾーンで守る相手の時と変わらず、1人がニアを抜けていくことで相手を引き出し、スペースにダイアーが入ってくるというものだ。そして、他の選手も各々マーカーを振り切ってニアに入ってくるという流れになるが、唯一ファーに流れる選手がいた。またもCKからゴールを奪ったケインである。

図6:第3節ウルヴァーハンプトン戦におけるCKの動き(攻撃側)
特にニアを狙うことが多いトッテナムにおいて、ファーに詰める選手がいるかどうかは重要だ。ニアで合わせたボールを逸らしすぎてファーに流れていったとしても、ファーに詰める選手がいればそれは絶好のアシストになる。
そしてファーへの入り方としては、基本的には最初からファーに入りすぎないということが大切だ。ウルヴァーハンプトン戦のようにマンマークの相手であれば、ケイン(図6の10番)のように一旦ゴールから離れる動きを入れて、相手のマークを外して飛び込んでいくことが多い。一方でサウサンプトン戦のようにゾーンで守る相手に対しては、遠くから飛び込んでいく動きを多用する。
このように、CKのほとんどをニアへ蹴るトッテナムにとって、ファーに詰めるケインはもうひとつの得点源になる。ちなみにほとんどの場合はケインがファーに流れるが、たまにケインがニアに合わせにいくこともあり、そのときは他の選手が代わりにファーに流れる。
・第4節 vsノッティンガム・フォレスト
ノッティンガム・フォレスト戦では、トッテナムはCKを1本しか得られなかった。そして、そのCKからカウンターを受け、自陣ボックス内まで運ばれてしまった。ここでは、攻撃時におけるカウンターのマネジメントについて見ていく。

図7:第4節ノッティンガム・フォレスト戦におけるCKの動き(攻撃側)
サウサンプトン戦のCKの節でも書いたが、トッテナムがより多くの人数をボックス内に送り込むのは、より多くの相手選手をボックス内に戻させるためなのではないかと筆者は考える。
しかし、それに従うかどうかはもちろん相手次第だ。ノッティンガム・フォレストは勇敢にもマンマークながらニアのカバーは1人だけ、そして2人を前に残すという形で守っていた(これを見た瞬間、筆者はトッテナムの次はフォレストのセットプレーを分析しようと心に決めた)。
それはさておき、この結果トッテナムは攻め残りに対して同数での対応を強いられることになった。
通常、攻め残りに対しては「プラス1人」で対応しようというのがセオリーだが、これは守備側がボックス内に2人以上の数的優位を確保しようとする場合にのみ適応される。多くのチームは、最低2人はニアと中央やファーなどにスペースを守る選手を配置する。
しかし、ノッティンガム・フォレストは1人しかスペースを守らない。当然攻撃側はキッカーを必ず1人用意しないといけないので、その他は9対9の同数になるのだ。これにより、トッテナムは相手の攻め残りに対して数的優位で対応するのは不可能となる。
さらにキックがGKにキャッチされるという、最悪の事態が起きてしまった。セットプレーにおいて、GKのキャッチはカウンターの発動条件である。そして、攻撃側は通常はカウンターに対応しないようなサイドバックやボランチ、小柄なアタッカーといった選手での守備を迫られるため、非常に危険な状況だ。しかしこの試合において、そのような状況の中でもトッテナムはよく守った。最終的にクロスまで持っていかれたものの、最後はボックス内に5人は戻せていたのでベターな対応はできていた。
さて、ノッティンガム・フォレストのカウンターの設計だが、(カメラに写っていないところがあるので初期配置は詳しくはわからないが)GKのキャッチから「横方向」の動き、つまり左右でポジションを入れ替えるような動きを多用していた。おそらく、同数となっている前線でポジションチェンジを起こすことで、それに釣られた守備陣に生じるマークのずれや、それに伴うスペースの創出を狙っていたのだろう。
だが、トッテナムはまっすぐ戻った。相手のポジションチェンジに対して基本的にマーク交換を行うことで、各選手が自分のレーンを縦に戻せるような対応をしていた。そのため、横の動きが多くなったノッティンガム・フォレストよりも早く縦に戻ることができ、さらにペリシッチの対応もあって事無きを得た。
第4節以外でこのようなカウンターを受けたシーンはほとんどなかったが、この場面を見てもトッテナムのCKからのカウンター対応はとても整理されていると感じられる。
・第5節 vsウェストハム
最後のウエストハム戦のCKは特に目新しいことはない。一応見ておくと、ソンとペリシッチがいる上でアウトスイングとインスイングを使い分けているものの、特に中の動きは変わらない。さらに4本ともニアで相手にクリアされたので、成功例はなかった。

図8:第5節ウエストハム戦におけるCKの動き(攻撃側)
図8のようにゴールエリア付近を固めるゾーン守備に対して、トッテナムの狙いは相手の背後から出てくることで優位に立とうというものだ。しかし、サウサンプトン戦やウルヴァーハンプトン戦のようにインスイングとセットで使われたのではなく、インスイングとアウトスイングのどちらも使用されていた。だが先ほども触れた通り、すべてニアで跳ね返されてしまったのでうまくいったとは言えない。
ここまでを振り返ると、トッテナムはCKの攻撃においてはニアをターゲットにして、基本的にインスイングならゴールエリア内から出ていく形、アウトスイングなら飛び込む形を採用することが多い。そこからニアで合わせてゴールを狙ったり、ファーに流れても誰かが詰められるような設計になっていると言える。
◇コーナーキック:守備
ここからは、CKの守備について見ていく。トッテナムは、基本的にスペースを守る選手が多く、ゾーンでの守備と言えるだろう。
配置としては、ニアポストに1人置き、4人のラインをゴールライン上に並べ、その前に3人のラインを作る。そして、2人がショートコーナー、セカンドボール回収要員としての配置をとる。
基本的にニアポストに入るのはエメルソンやセセニョンで、4人のラインはニアからホイビュアー、ケイン、ダイアー、そしてもう1人のボランチかウイングバックが並ぶ。その前の3人のラインには、ニアにデイビス、そしてもう1人のセンターバックとボランチかウイングバックが入る。ショートコーナーやセカンドボール対応は、ソンとクルゼフスキの両シャドーが務める。
そして、カウンターには両シャドーに加えニアのホイビュアーが参加することが多い。以下の図9は、チェルシー戦における前半41分のCKを示す。

図9:第2節チェルシー戦におけるCKの動き(守備側)
このシーンはファールで止められて終わるが、他にもケインが後ろから加わるなど、クリアボールからのカウンターを狙っている。
第5節まででトッテナムは、CKからの失点はない。では、トッテナムのCKの守備における弱点はどこにあるのだろうか?おそらく、明確にその弱点を狙い続けていたのはノッティンガム・フォレストだろう。

図10:第4節ノッティンガム・フォレスト戦におけるCKの動き(守備側)
図10のように、ノッティンガム・フォレストはファーへのストレートボールを折り返すという狙いを持っていた。これには、守備の構造上の弱点を突く効果がある。まず、ゾーンで守るトッテナムに対して後方から飛び込むことで、その場に立ったままでの対応になるトッテナムの選手に対してフィジカル面で上回れる可能性が高くなる。さらに、ファーへのボールに対しては下がりながらの対応になるので、よりクリアするのが難しくなる。
もしかするとファーの選手は身長が低くてそこを狙っているとも言えるのか、と思い身長を調べたところ、ペリシッチが186cm、ベンタンクールが187cmといった具合で高身長の面子が揃っており、181cmのデイビスとエメルソンは仲良くニアを担当させられている。ただ、ペリシッチではなく178cmのセセニョンが出てくるという想定をした場合、ファーには181cmのエメルソンが回ってくることが多いので狙えそうな気がしなくもない。ただ、競り合いは身長だけではないので、その辺りは攻撃側の選手の持っている武器との相談である。
◇フリーキック:深い位置
ここからは、フリーキック(FK)について分析していく。しかしFKはCKと比べて蹴られる位置はバラバラかつ本数も少ないため、5試合だけではサンプル不足という印象は否めないが、ひとまずここまでの情報をまとめてみよう。本稿では、FKを開始する位置と攻守それぞれの場合に分け、計4パターンで見ていく。
・深い位置からのFK(攻撃)
、まず深い位置からのFKだが、基本的にCKと似た考え方になる。下の図11はウルヴァーハンプトン戦のFKである。

図11:第3節ウルヴァーハンプトン戦におけるFKの動き(攻撃側)
ゾーンで守る相手に対して、背後から顔を出すことで守備者の前で触れるようにしたり、ペリシッチがニアを抜けることで相手を引き出したりと、CKで見たような流れが深い位置でのFKにも採用される。チェルシー戦でも深い位置からのFKがあったが、どちらも狙いはニアという点も共通している。
煩雑化を避けるため図11では省いているが、矢印の出ていない中の3人(33番・6番・30番)も全員ニアから中央にかけて飛び込んできている。また、それぞれがどの隙間に入るのかはあらかじめデザインされていたのだと考えられる。
・深い位置からのFK(守備)
守備においても、攻撃と同様にCKと似た狙いがある。違いとしては、壁とオフサイドの存在だろう。図12は、サウサンプトン戦のFKである。

図12:第1節サウサンプトン戦におけるFKの動き(守備側)
壁に入るのはCKでニアポストを担当していた選手。ラインの高さは壁と同じくらいで、5人が並ぶ。CKと同じ4人に、ケインとダイアーの間にボランチのベンタンクールが加わる形だ。
そして、CKで3人のラインを形成していた残り2人がラインの手前に入るのだが、少しマンマーク気味に対応しているように見えた。しかしサウサンプトン戦では、CKの守備においてもこの2人の選手は他の試合に比べて人を意識したような守備をしていたため、この試合限定の対応かもしれない。
◇フリーキック:浅い位置
・浅い位置からのFK(攻撃)
さて、続いては浅い位置からのFKについて見ていく。以下の図13は、チェルシー戦のFKだ。

図13:第2節チェルシー戦におけるFKの動き(攻撃側)
この試合は、CKの分析で記述した通りインスイングにこだわった試合で、ソンが左足でボールを入れる。残念ながらボールが浮いて流れていく形になったが、狙いとしてはニアで触ってもよし、流れてファーでもよし、といったボールだろう。
ファーにはベンタンクールとロメロがシンプルに走り込む形で、中央にもダイアーがまっすぐ入ってくる。一方、ニアはデイビスとホイビュアーが相手をブロックしたところをケインが走り込むという形を取り入れていた。
このようなFKで一番多い守備側の対応が、ニアでクリアする形だ。守備側からすると、ニアを通過すれば攻撃側選手の誰かに合わせられる可能性が上がり、下がりながらの難しい対応を迫られるためだ。そのため、攻撃側はニアの相手をブロックするといった工夫をしているのではないだろうか。
・浅い位置からのFK(守備)
最後に、浅い位置からのFKにおけるトッテナムの守備について見ていく。

図14:第2節チェルシー戦におけるFKの動き(守備側)
深い位置のFKの守備時と同じく、CKの守備においてゴール前に4人と3人のラインを形成していた7人がラインを形成。その他の3人で、壁やセカンドボール回収要員を務める。
そして、ラインの高さは壁よりは少し低いくらいで揃え、キッカーの助走1歩目からラインを下げ始める。また、セカンドボールに対してのラインアップもダイアーを中心に行うが、ボックスの高さまで上げることはほとんどなく、セカンドボールが回収されてクロスを上げることができるタイミングでラインを止めている。
トッテナムは全体的に、背後へのスペースを空けるリスクは負わない傾向にある。ダイアーは積極的にラインを上げようと味方に指示を出していることが多いが、他の選手は対面の味方のことを意識して動くことが多い。
◇おわりに
「4,830通りのセットプレーがある」とも言われているジャンニ・ヴィオが率いるトッテナムのセットプレーは、多種多様なパターンや奇抜なルーティーンを用いるというよりも、シンプルに的確に相手の弱みを突く狙いがうかがえる。
チェルシー戦やウルヴァーハンプトン戦はセットプレーで勝ち点を拾った試合ともいえる内容で、既にヴィオは大きなインパクトを与えることに成功している。これからの対戦相手に対してこれまでの5試合の中で見せなかったような対策をとるのか、それとも今の道を貫いていくのか。
今季のプレミアリーグ、ぜひ読者の皆様もトッテナムのセットプレーに注目していただきたい。
(編集部注:9月17日に行われたばかりのレスター・シティ戦でもトッテナムはCKから2得点を挙げ勝利。ヴィオのかけた“魔法”に注目が集まっています)


Both deserve huge credit for Spurs' 6-2 win against Leicester.
@harryedwards16 can tell you why...
文:白水優樹(@shiroe___s)
ディ アハト第80回「チーム分析:トッテナム / ジャンニ・ヴィオ[セットプレー]」、お楽しみいただけましたか?
記事の感想については、TwitterなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!
ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら